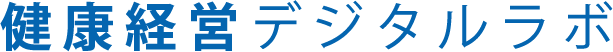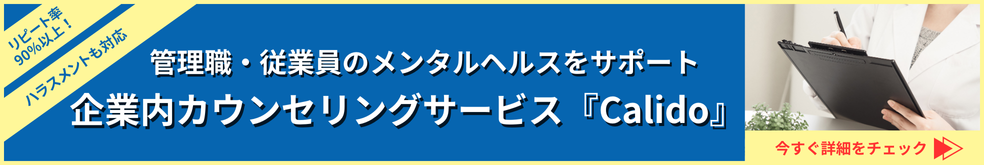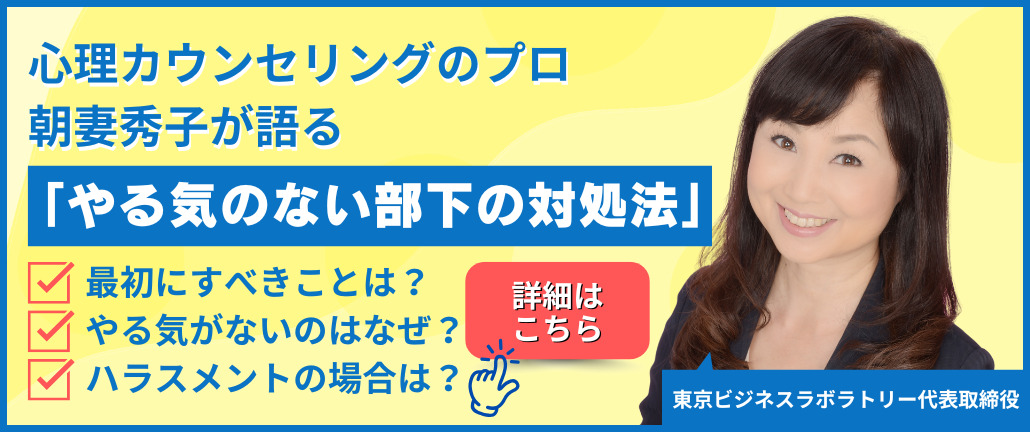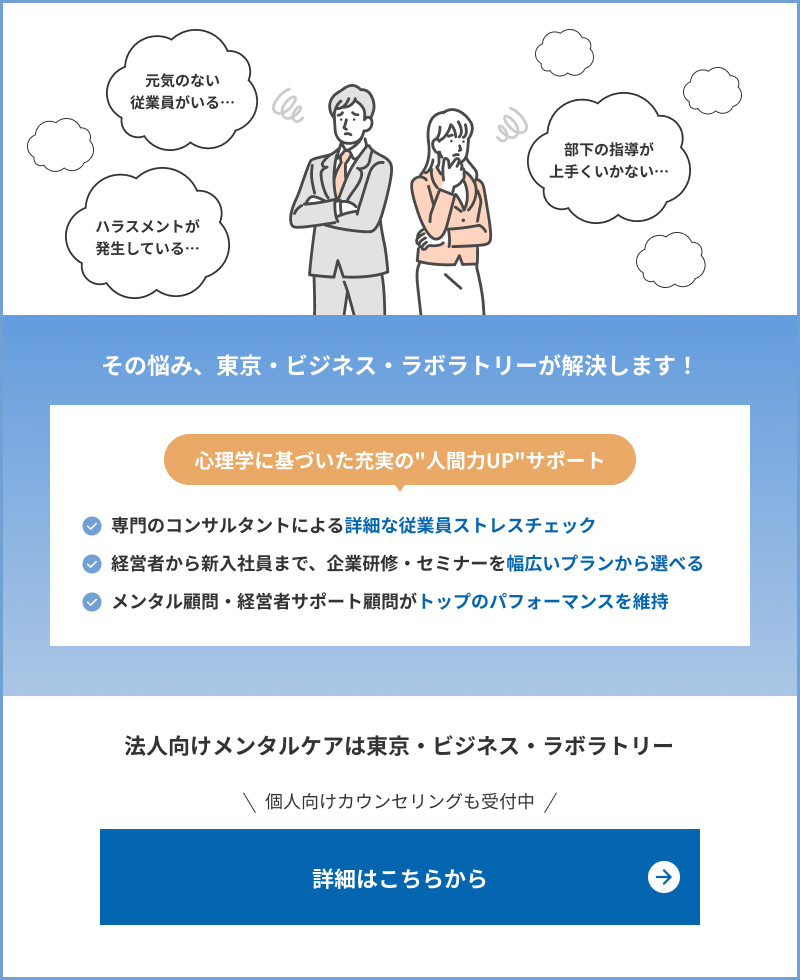目次
部下が言うことを聞かない原因

部下が言うことを聞かない原因が、何なのかわからないという方も多いでしょう。主な原因として、次の2つがあげられます。
・部下に存在を軽視されている
・部下との信頼関係ができていない
原因がわかれば、対処方法も見えてくるかもしれません。それぞれの詳しい内容について解説します。
部下に存在を軽視されている
部下が言うことを聞かない原因のひとつに、上司として存在を軽視されている可能性があります。直接的に部下の評価をする人に対して、言うことを聞かない部下は少ないものです。
しかし、そんな存在になれていないのだとしたら「この人の言うことは聞かなくても大丈夫」と思われているのかもしれません。例えば、普段から強く言えなかったり遠慮してしまったりしていると、そのうち部下は言うことを聞いてくれなくなります。
また、上司として正しい指摘ができないことも原因にあげられるでしょう。その結果として、部下に存在を軽視されるケースもあります。指摘することはなかなか気力のいることですが、部下の成長のためにも、最低限の指摘はできるようにしましょう。
部下との信頼関係ができていない
部下が言うことを聞いてくれないのは、信頼関係が築けていないからかもしれません。
例え、正しいことを言っていたとしても、信頼関係がないと、素直に受け取ってもらえないこともあるでしょう。そのため、まずは「この人の言うことを聞こう」と思ってもらえるような、信頼関係を作る必要があります。
部下が話を聞いてくれないのは、言葉や態度に不満があるからかもしれません。
例えば、部下に対して「言うことを聞くのが当たり前だ」と思って接していると、相手は不満を感じ、信頼関係を築けなくなります。
部下が言うことを聞いてくれないと感じるなら、日ごろの部下への態度を振り返ってみましょう。
信頼関係は最初のうちに作っておかないと、後々に作るのは難しくなるものでもあります。後述する対策を取り入れて、部下との信頼関係を築いてみてください。
言うことを聞かない部下を放置する危険性

言うことを聞かない部下への対処を先延ばしにしたり、問題を見て見ぬふりをしたりすることは、単にその部下一人の問題にとどまりません。
ここでは、問題のある部下を放置することで生じる3つの主要な危険性について詳しく解説します。
上司への信頼失墜
問題行動を見過ごす上司は、他の部下から「適切に対応できない管理職」として認識され、リーダーシップに対する信頼を著しく失うことになります。
部下たちは日常的に上司の判断力や行動力を観察しており、明らかな問題に対して何も対処しない姿勢を見せると、「この上司は頼りにならない」という評価が定着しかねません。
一度失った信頼を回復することは極めて困難であり、今後の指示やアドバイスも軽視されやすくなってしまいます。部下からの報告や相談も減少し、重要な情報が上がってこなくなるという悪循環に陥る可能性があります。
組織全体の規律や士気の低下
特定の部下が指示を無視する行動を放置すると、それを目撃した他の社員たちに「真面目に取り組む必要がない」という誤ったメッセージを送ることになります。
最初は一人の問題行動であっても、適切な対処がなされないと、他の社員も同様の行動を取るようになります。「あの人が許されるなら、自分も同じことをしても大丈夫だろう」という心理が働き、次第にチーム全体の規範意識が低下していくのです。
真面目に業務に取り組んでいる社員ほど不公平感を強く感じるようになり、組織への帰属意識や仕事への意欲が削がれてしまいます。
離職リスクの増大
不公平な環境や規律の緩んだ職場に対する不満が募ることで、特に優秀で責任感の強い人材ほど退職を検討するようになります。こうした人材は公正で秩序のある環境を重視する傾向があり、問題行動が野放しにされている組織に対して強い失望を感じるためです。
また、優秀な人材の退職は他の社員にも心理的な影響を与え、「この会社に将来性はないのではないか」という不安を抱かせる要因にもなります。
さらに深刻なのは、優秀な人材が抜けた後の業務負担の増加です。残された社員に過度な負荷がかかることで、さらなる離職を招くという負のスパイラルに陥る可能性があります。
部下とコミュニケーションを取るポイント
部下とコミュニケーションを取るポイントには、次の7つがあります。
・部下のタスクの把握に努める
・意識的に褒める
・相手に寄り添いながら、望んでいることをきちんと伝える
・普段の行動をワンランク上げる
・誰にでも敬意を払う
・注意とフォローを上手に使う
・心理的安全性を意識する
はじめは言うことを聞いてくれなかったとしても、部下とのコミュニケーションがうまく取れるようになると、少しずつ言うことを聞いてくれるようになる場合も多くあります。部下が言うことを聞いてくれるようになると仕事がスムーズに進み、ストレスも減るはずです。
ここでは、ポイントごとに詳しい内容を見ていきましょう。
部下のタスクの把握に努める
上司は自分だけでなく、部下のタスクを把握するのも大切です。部下のタスクやスケジュールを把握すればその都度、進捗の確認や報連相をしやすくなります。
報連相は部下からするものだと考える方もいるかもしれませんが、ただ報告を待つのではなく、上司から声掛けすることも大切です。そうすれば「気にかけてくれている」という安心感を持ち、部下としても相談を持ち掛けやすくなるでしょう。
また、業務に関する話だけでなく、体調やメンタルヘルスを気遣うなどのコミュニケーションの幅を広げれば、徐々に信頼関係が作られます。
褒めることを意識的に行う
部下を褒めることも、コミュニケーションで大切なポイントです。上司に褒められるのは、部下にとって嬉しいものといえます。褒められることで部下の承認欲求が満たされ、やる気が出たりモチベーションが高まったりするでしょう。
その結果、意欲的に取り組んだり、自ら動いてくれたりするなど、部下の自発的な行動にもつながります。褒めるときには、次のポイントを意識してみてください。
・良いことをしたときに褒める
・人そのものを褒める
・行動を褒める
・失敗したときも褒める
・過程を褒める
「報告書作成といえば、○○さんだね」や「○○さんの発想力はすごいよね」などと、具体的な言葉で伝えるとより効果的です。
褒めることで受け手側のモチベーションが上がるだけでなく、発信する側も自身の成長に対するポジティブな思考を育てられます。日常的に「褒める」ことを心がけ、部下とのコミュニケーションを深めましょう。
相手に寄り添いながら、望んでいることをきちんと伝える
部下への指示は必ずしも厳しい口調で行う必要はありません。やさしい口調であっても、内容を具体的に伝えることの方がはるかに重要です。
具体的な目標設定、明確な成果物の定義、達成期限の明示など、詳細な情報を提供することで、部下は自信を持って業務に取り組むことができるようになります。
また、指示を出す際には部下の状況や能力を理解し、個々のレベルに応じた適切な難易度で伝えることも大切です。相手に寄り添った姿勢を示すことで、部下は上司の期待に応えようとする意欲が高まります。
普段の行動をワンランク上げる
上司の何気ない日常的な行動は、部下にとって重要な手本となります。そのため、部下に変化や改善を求める前に、まず上司自身が意識や行動を見直し、向上させることが不可欠です。
言葉で伝える指導よりも、実際の行動を通じて示す姿勢の方が、部下により強い影響とメッセージを与えることができます。
例えば、時間管理の徹底、丁寧なコミュニケーション、継続的な学習への取り組み、責任感のある行動など、すべての面において上司自身がより高い基準で行動することが重要です。部下は上司の背中を見て学び、その姿勢を模倣する傾向があります。
誰にでも敬意を払う
部下に対してはもちろん、誰に対しても敬意を払うことは人付き合いにおいて大切なポイントです。部下と上司は、あくまでも役割分担でしかありません。
「人」として接している以上、敬意を払って関わる必要があります。敬意が相手に伝わらないことで、最終的には部下が言うことを聞かなくなるケースも少なくありません。
特に、管理職になりたての頃は部下に対して強く出てしまう方もいます。しかし、部下に対しては「仕事をして当たり前」の態度ではなく、感謝の気持ちをもって接することが大切です。
会社は、お互いの信頼関係や役割分担で成り立っています。部下だけでなく、誰に対しても敬意を払って接することで、仕事も人間関係も円滑に進むようになるでしょう。
注意とフォローを上手に使う
部下に対して、いつでも甘い顔をすると存在の軽視につながります。そのため、業務の中で部下が良くないやり方や態度をとったときには、きちんと注意するようにしましょう。
ただし、「注意するときにはほかの社員がいないところで注意する」や「自分の主観を入れず簡潔に伝える」といった細かな配慮も必要です。また、何に対して注意したのかがわかるようにしっかり言葉にしましょう。
注意をしたあとは、フォローも忘れてはいけません。注意された側は気分が落ち込み、職場の雰囲気も悪くなってしまいます。やる気を失ってしまう部下もいるかもしれません。そんな場合は、自分から明るく声掛けをすると良いでしょう。
さらに、注意する際は「こういうところは良くなかったけれど、ここは良かった」などと、頑張りや過程などを認め、褒めるようにします。注意した部分が改善されたときは、その点を褒めてあげるのも大切です。
心理的安全性を意識する
心理的安全性の高い職場環境を構築することは、部下との良好なコミュニケーションを実現するための重要な要素です。まず、発言しやすい雰囲気づくりや定期的な対話の場を設け、チーム全員が平等に意見を言えるよう配慮することが必要です。
階層や経験年数に関係なく、すべてのメンバーが自分の考えを自由に表現できる環境を整えることで、創造的なアイデアや建設的な意見交換が促進されます。
また、部下の意見や努力を積極的に認め、日頃から感謝の気持ちを伝えることで、部下は「自分は尊重されている」と感じ、心理的安全性がよりいっそう高まります。このような環境では、部下は失敗をおそれることなく挑戦し、率直に意見を述べられるようになります。
上司としての人間力を高めて部下との関係構築を図ろう
部下との関係構築をうまく図っていきたい方のスキルアップのため、「東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)」では企業研修を実施しております。
上司としての人間力を高めるサポートだけでなく、新入社員の新しい環境へ適応するマインドや経営者の決断力などを、心理学のメソッドで学べる研修です。
勤務年数や役職に応じたメンタル面を支えるさまざまなセミナーを開講しているため、ぜひ以下から詳細をご覧ください。
>>東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の研修・セミナーの詳細はこちら
まとめ
部下が言うことを聞いてくれないとき、上司の態度や言動が原因の可能性もあります。
部下への対応がうまくできれば、自身の上司としての価値を高められます。この機会に職場での発言や行動を見直し、改めて部下との信頼関係を構築していきましょう。