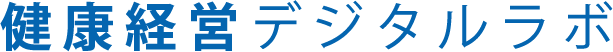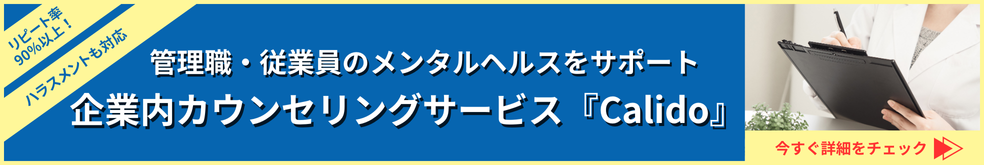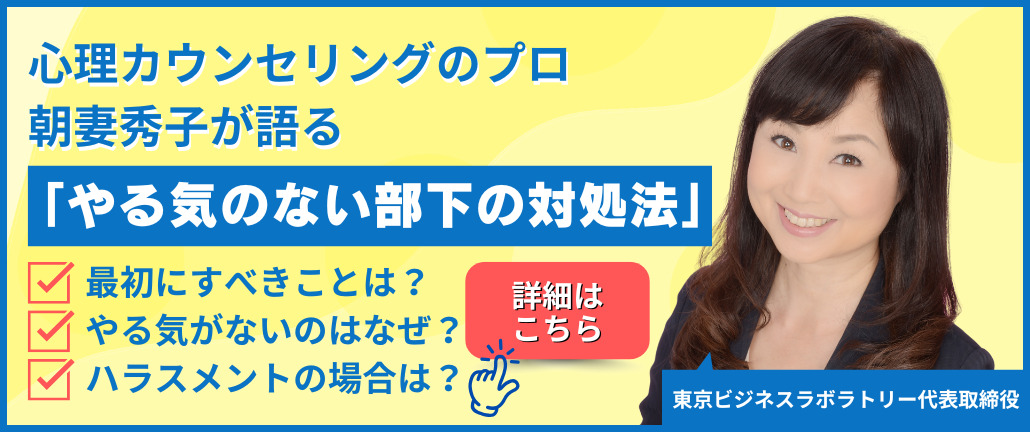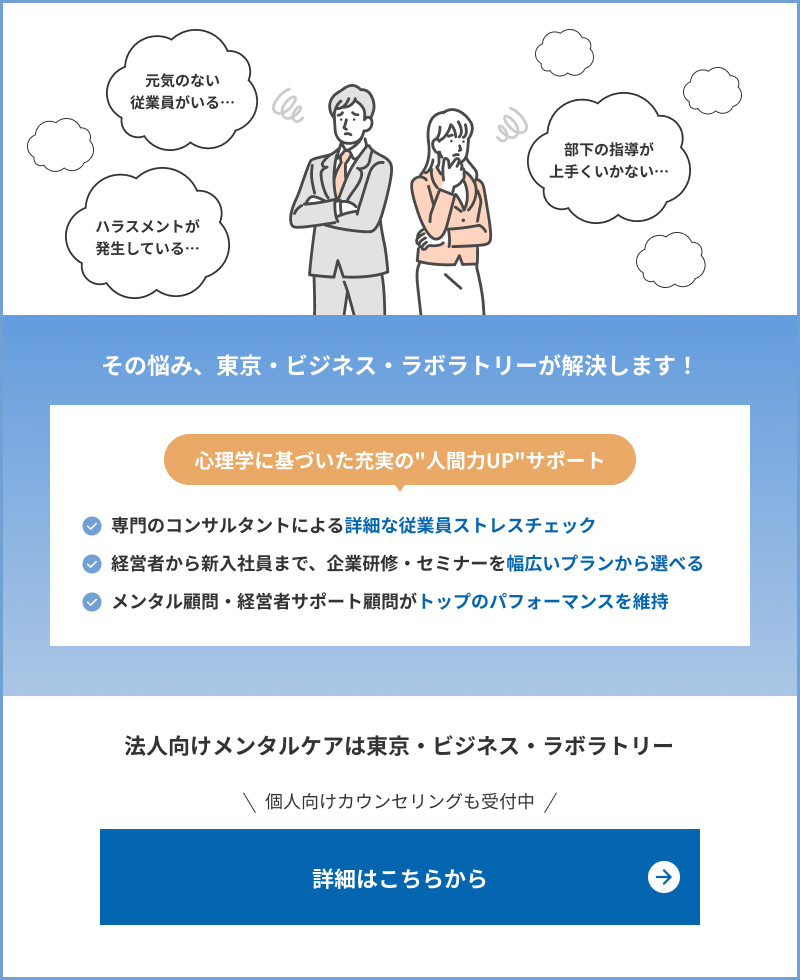目次
心理的安全性の測定方法

まずは心理的安全性を測定するための方法をみていきましょう。
心理的安全性を測定する7つの質問
心理的安全性を測定するには、心理的安全性を提唱したハーバード大学の教授、エイミー・エドモンドソン教授による下記の7つの質問を用いるのが基本的な方法です。
2.チームのメンバー同士で難しい問題・課題について指摘し合える
3.チームのメンバーは、自分の考えと異なるという理由で他者を拒絶することがある
4.チーム内でリスクがある行動を取っても安全である
5.チームのメンバーに助けを求めにくい
6.チームのメンバーに自分を意図的に貶めたり騙したりする人はいない
7.チームのメンバーと働くときに自分のスキルや才能が生かされている、尊重されていると思う
上記は、従業員が職場で感じる安全感や信頼感を多角的に測定するように設計されています。各質問は、心理的安全性を構成する要素を反映しており、組織の現状を客観的に把握するための有効な指標となります。
7つの質問の活用方法
心理的安全性を測定するには、7つの質問を用いたアンケートを実施すると良いでしょう。具体的な実施方法は以下の通りです。
7つの質問に対して「まったくそのとおりだ」から「まったくそのとおりではない」までの7段階評価をし、点数付けを行います。この際、質問の性質を理解することが重要です。
質問1、3、5はネガティブな質問であり、スコアが低いほうが良い結果を示します。一方、質問2、4、6、7はポジティブな質問であり、スコアが高いほうが良い結果を表します。
ポジティブな質問のスコアが高い組織は心理的安全性が高く、逆にネガティブな質問のスコアが高い組織は心理的安全性が低いといえます。組織の現状を数値で把握し、他部署や過去の結果との比較も可能になります。
アンケートよりも精度は落ちますが、1on1ミーティングなどで7つの質問をする方法もあります。この場合、より詳細な回答を得ることができ、個人の状況をより深く理解することが可能です。
心理的安全性が低い職場の特徴

7つの質問で測定する以外に、心理的安全性が低い職場の特徴に該当していないかどうかをチェックすることも重要です。ここでは、心理的安全性が低い職場でよくみられる特徴を紹介しましょう。
ミスを報告せず隠す傾向にある
心理的安全性が低い職場では、ミスを報告せず隠す従業員が多くなります。これは、無能だと思われる不安を感じるためです。従業員は失敗を認めることで評価が下がることを恐れ、問題を一人で抱え込んでしまいます。
この結果、問題が大きくなってから発覚することが多く、ミスを通じた改善の機会が失われてしまいます。本来であれば、小さなミスは組織全体の学習機会として活用できるはずですが、隠蔽されることで貴重な改善のチャンスを逃してしまうのです。
問題・課題について話し合う機会が少ない
心理的安全性が低い職場では、課題や問題を自由に話し合う場が少なくなります。従業員は問題を抱え込むことが多く、早期に解決されないため、業務効率の低下や組織の停滞を招きます。
また、意見を交わすことがほとんどないため従業員同士の信頼関係が築かれにくく、離職率の上昇につながる場合もあります。オープンなコミュニケーションが阻害されることで、組織全体の問題解決能力が低下してしまいます。
新たなアイデアや提案が出にくい
心理的安全性が低い職場では、従業員が新しい意見やアイデアを発言しにくくなります。これは、変化を避け、現状維持を好む傾向が強く、発言によってチームから拒絶されることを恐れるためです。
イノベーションや改善は、多様な意見やアイデアから生まれることが多いため、このような環境では組織の成長が停滞してしまいます。従業員の創造性や積極性が抑制されることで、競争力の低下にもつながりかねません。
従業員が自分の意見を主張しない
心理的安全性が低い職場では、従業員が自己主張することに強いプレッシャーを感じます。自分の意見を拒絶されたり、邪魔をしていると思われたりするのではないかと不安に思うためです。
会議や日常の業務においても、意見交換が少なくなり、組織全体の活気が失われます。多様な視点や意見が交換されないことで、意思決定の質が低下し、組織の成果にも悪影響を与えることがあります。
社内のコミュニケーションが少ない
心理的安全性が低い職場では、従業員同士のコミュニケーションが少なくなります。無知だと思われる、ネガティブにみられるなどの不安で質問や相談がしづらくなるためです。
こうした状況では、組織の連携が悪くなり、業務がスムーズに進まなくなります。情報共有が不十分になることで、重複作業や連携ミスが発生し、全体的な生産性が低下してしまいます。
心理的安全性の測定結果が低かった場合の対処法

心理的安全性の測定結果が低かった場合、以下の対処法を実施することで改善を図ることができます。
なお、心理的安全性を高める方法についてはこちらの記事でも解説しています。
「心理的安全性が低い職場の原因とは?放置するリスクや高める方法を解説」
質問・相談しやすい環境をつくる
わからないことがあったら質問できる、ミスを起こしたときに相談できるという環境になれば、心理的安全性が上がります。上司や先輩など、立場が上の側から声かけをしたり見守っている姿勢を示したりすることが重要です。
具体的には、定期的な声かけの仕組みを作る、質問を歓迎する文化を醸成するなどの取り組みが効果的です。従業員が安心して発言できる環境を整えることで、組織全体のコミュニケーション活性化につながります。
フォローやサポート体制を整える
孤立感が払しょくされると心理的安全性が高まります。1on1ミーティングを実施する、定期的にフィードバックする時間を取る、悩み相談の窓口を設置するなどが有効です。
また、新人向けにメンター制度を導入するのも良いでしょう。上下関係を意識しすぎず、気軽に相談できる相手をつくることで、従業員の安心感を高めることができます。継続的なサポートを通じて、従業員が困難に直面したときでも一人で抱え込まずに済む環境を構築できます。
チームで共通の目標を立てる
チーム全体の共通目標を立て、目標達成に必要な言動は何かを共有することが大切です。価値観が統一されていると、自分と異なる意見や指摘を個人攻撃と捉えにくくなります。
共通の目標があることで、積極的に発言しやすくなり、社内のコミュニケーションが活性化します。目標達成に向けて建設的な議論が生まれやすい環境を整えることで、チーム全体の結束力も高まります。
チームを再編する
いろいろと試しても心理的安全性が向上しない場合、チームメンバーの相性が悪い可能性があります。どうしても状況が改善しないときは、メンバーの入れ替えも検討する必要があります。
相性が良いメンバーが集まるとコミュニケーションが円滑になるので、心理的安全性が高まります。ただし、組織全体への影響も考慮しながら、慎重に検討しましょう。
個人の意識改革を行う
チームの心理的安全性を高めるためには、個人の意識改革も重要です。心理的安全性を高める施策をどれだけ行っても、個人がそれを受け入れる状態を整えていなければ、うまく機能しないからです。
自分で考え動ける「自律型人材」を育成することで、組織全体の心理的安全性向上につなげることができます。研修やワークショップを通じて、従業員の意識改革を促進していくことが効果的です。個人の成長と組織の発展を両立させる取り組みが求められます。
自律型人材の育成なら、東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)にお任せください。経営方針・現状の課題をヒアリングしたうえで、それぞれの企業様に最適化した研修を提供いたします。
まとめ
心理的安全性の測定は、エイミー・エドモンドソン教授の7つの質問を活用することで客観的に行うことができます。測定結果が低い場合は、質問・相談しやすい環境づくり、サポート体制の整備、共通目標の設定などの対処法を実施することで改善が可能です。継続的な測定と改善により、生産性向上と離職防止を実現しましょう。