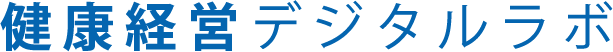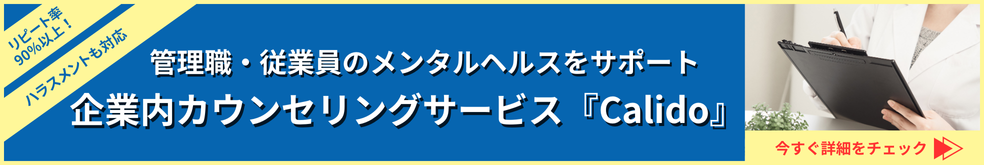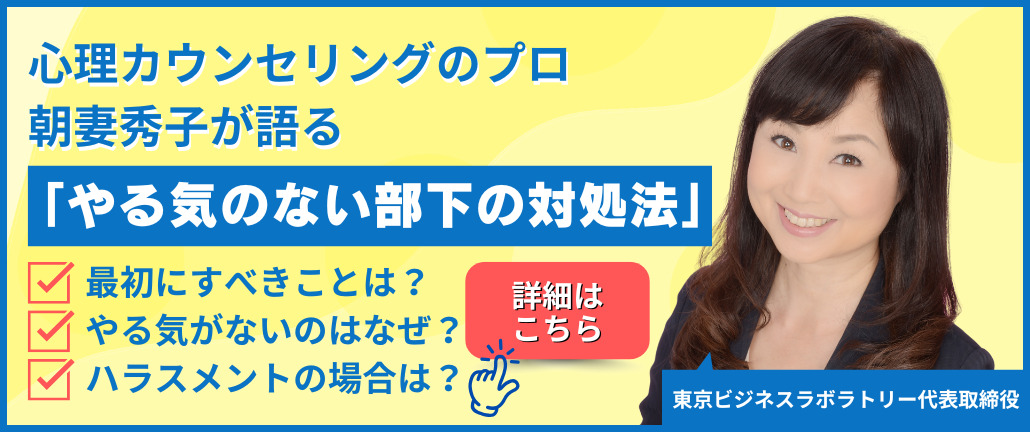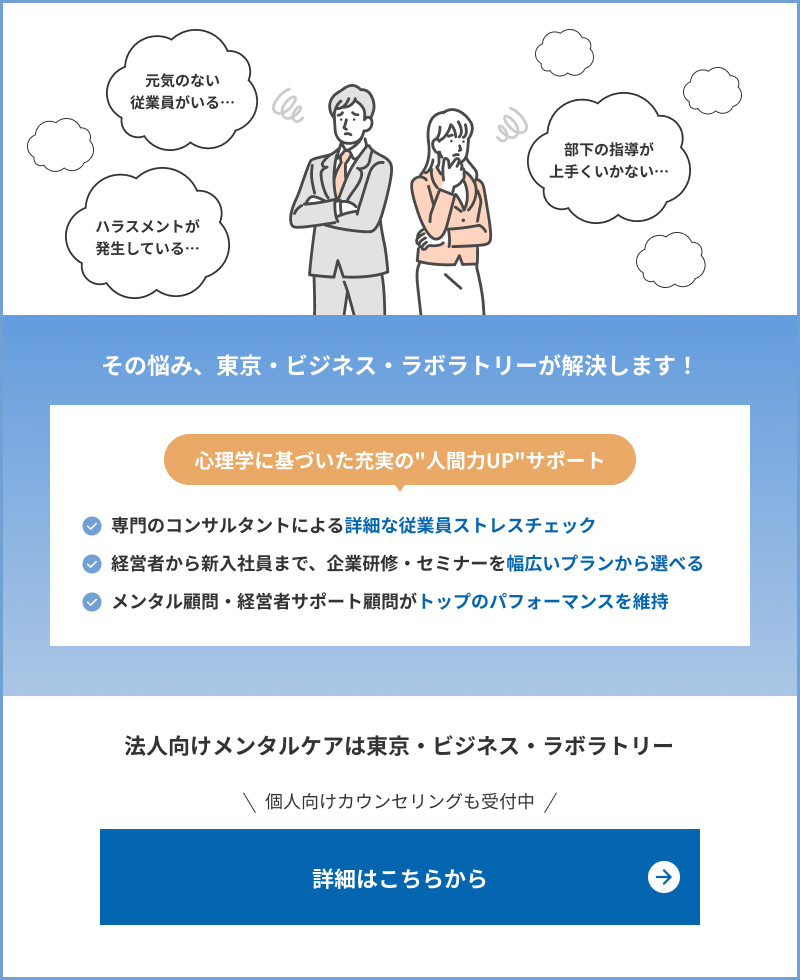目次
スキルズインベントリーとは

スキルズインベントリーとは、従業員のスキルや知識、経験、能力、業務内容などを一元的に記録・管理するデータベースです。企業にとっては「人材のスキル台帳」となり、人事戦略や組織運営の基盤となります。
直感ではなくデータに基づいて「誰が何をできるか」を把握できるため、適材適所の配置や育成計画の立案、採用条件の明確化が可能になります。
登録するスキルには、ヒューマンスキル、テクニカルスキル、職種を越えて活かせるポータブルスキルなどがあり、これらを体系的に整理して活用します。
スキルズインベントリー作成によるメリット
ここからは、スキルズインベントリーの導入で得られる代表的な5つのメリットを解説します。
組織全体の能力の把握と強化
スキルズインベントリーは、社員一人ひとりのスキルを集約し、組織や部署ごとのスキル総量や強み・弱みを可視化します。可視化により、組織の課題や強化ポイントを客観的に把握でき、具体的な改善策を立てやすくなります。
例えば、営業部門で特定の業界知識が不足している場合、その分野の研修を集中的に実施するなど、的確な対策が可能です。さらに、過去のデータとの比較で、組織全体の成長度合いや研修効果を数値として確認できるようになります。
適材適所の人材配置が可能
データとしてスキルを管理すると、どの部署にどの能力が不足しているかが明確になります。その結果、異動や配置転換の際に、適切なスキルをもつ人材を最適な部署に配置でき、業務効率や成果の最大化につながります。
例えば、新規事業部立ち上げ時に必要なデジタルマーケティングや海外営業の経験者を素早く特定できるなど、スピード感ある対応が可能です。
適切な能力評価
スキルズインベントリーがあれば、評価基準が明確になり、評価する側とされる側の間で認識のズレが減ります。従業員にとっても、自分の強みや改善すべき点が明確になり、成長に向けた行動計画を立てやすくなります。
評価の透明性が高まれば、モチベーションの向上にもつながります。また、評価結果を過去のデータと比較し、長期的な成長度合いや成果を定量的に示すことも可能です。
人材育成計画の効率化
現状のスキルマップと理想の状態を比較することで、育成すべき分野が明確になります。研修やスキルアップ計画を的確に立案でき、限られた予算や時間を効果的に活用可能です。
例えば、営業スキルが高い社員が多い一方で、分析力が不足している場合は、データ分析研修を優先的に実施するといった判断が容易になります。
教育費の適正化
スキルの保有状況を把握しておけば、すでに習得している内容の研修を重複して実施する必要がなくなります。従業員に必要な教育だけを行うことで、無駄な教育コストを削減しつつ、研修効果を最大化できます。
さらに、研修後の効果測定とスキルデータの更新をセットで行えば、投資対効果を明確に把握できます。
スキルズインベントリーの作成手順

スキルズインベントリーは、以下の4つのステップで構築するのが効果的です。
1.目的を明確に設定する
まずは「なぜスキルズインベントリーを作成するのか」という目的を明確にしましょう。人材育成のためなのか、配置転換のためなのか、採用戦略のためなのかによって、収集すべき情報や評価項目が変わります。
目的は作成に関わる全員と共有し、共通認識を持つことが重要です。目的を曖昧にしたまま進めると、データが形骸化し、活用されなくなるおそれがあります。
2.業務内容やスキル、階層を決定する
職種ごとに必要なスキルを洗い出し、業務ごとに整理します。その際、すべてを網羅しようとせず、目的に沿って収集項目を絞るのがポイントです。
また、スキルを初級・中級・上級などの階層に分け、現状レベルや不足スキルを明確に把握します。例えば「英語スキル」を階層化すれば、日常会話レベルの人材とビジネス交渉レベルの人材を瞬時に判別できます。
3.評価基準を設定する
評価は誰が見てもわかるように数値化し、明確な基準を設けます。例えば、業務遂行能力を4段階評価にするなど、客観性と公平性を担保することが大切です。基準が曖昧だと、評価者によって判断が異なり、制度の信頼性が損なわれます。評価基準は現場の声を反映し、定期的に見直すことも重要です。
出典:厚生労働省「職業能力評価基準」
4.試験運用を行う
いきなり全社導入するのではなく、一部部署で試験的に運用し、改善点を洗い出します。その後、記入方法や評価基準をわかりやすくまとめたマニュアルを作成し、本格導入します。試験運用でのフィードバックを反映させることで、制度が現場に浸透しやすくなります。
従業員のスキルの把握方法

スキル情報を正確に収集するためには、複数の方法を組み合わせるのが効果的です。
人事や上司との面談
人事担当者や直属の上司が従業員と面談し、経験や得意分野、キャリア志向などをヒアリングしてスキルを把握する方法です。直接の対話で本人の考えや意欲を把握でき、配置や育成方針の参考になります。ただし、評価者の主観が入りやすく、質問内容や評価基準が統一されていないと正確なデータが得られない場合もあるため、事前準備が重要です。
社員の自己申告
チェックリストやアンケートを活用し、従業員自身にスキルや経験を申告してもらう方法です。自己認識を整理する効果もありますが、過大評価や過小評価の可能性もあるため、客観的評価との組み合わせが必要です。
360度評価
上司・同僚・部下など、複数の立場から従業員を評価する手法です。自己評価だけでは見えにくい行動特性やスキルを多角的に把握でき、公平性と納得感の高い結果が得られます。
特に、コミュニケーション力やチームワークなど数値化しづらい能力の評価に有効です。また、自己評価との差から課題や強みを再認識でき、成長計画の立案にも役立ちます。実施時は匿名性の確保や目的の周知を徹底し、信頼性の高いデータ収集を行うことが重要です。
スキルズインベントリーを有効に活用するコツ
スキルズインベントリーを作成しても活用できなければ意味がありません。ここでは有効に活用するコツを解説します。
会社全体で取り組む
作成したスキルズインベントリーは、部署単位ではなく全社的にスキルを共有し、組織全体の最適化を目指します。他部署間でスキルを活用できれば、人材活用の幅が広がります。
例えば、営業部門で語学力のある人材を海外事業にも関わらせられれば、既存人員のまま新規案件に対応できるなど、機動力が高まります。定期的に全社ミーティングや社内ポータルを通じて最新のスキル情報を共有すると効果的です。
成果と連携する
スキル評価を昇進・昇格や業績評価と結びつけることで、従業員がスキルアップの成果を実感しやすくなります。
例えば、管理職昇格条件として「スキルズインベントリー上でレベル3以上のリーダーシップ評価」を設定すれば、評価制度と明確にリンクでき、社員の成長意欲を高められます。
客観的な基準を設定する
誰が見ても同じ評価ができるよう、明確で数値化された基準を設定します。評価基準の設定は制度への信頼性が高まり、従業員も納得して取り組めます。また、基準は固定化せず、業界トレンドや社内の事業戦略に合わせて更新し、常に現場の実態に即した評価を可能にしましょう。
まとめ
スキルズインベントリーは、人材のスキルを可視化し、組織の課題解決や成長戦略に活かせる強力な仕組みです。配置や評価、育成のすべてにおいて精度が高まり、結果的に組織力の向上につながります。
リーダーシップ研修やハラスメント研修など、組織として弱い部分のスキルに応じてカスタマイズした研修をお求めなら、東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の実践的でカスタマイズ可能なプログラムをぜひご検討ください。