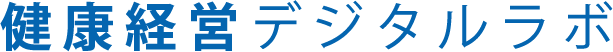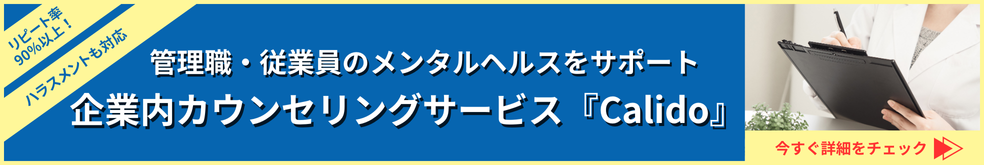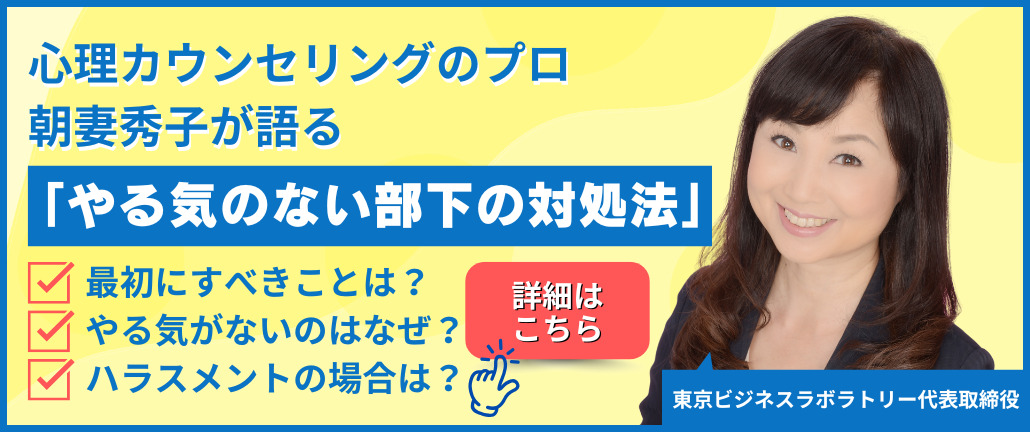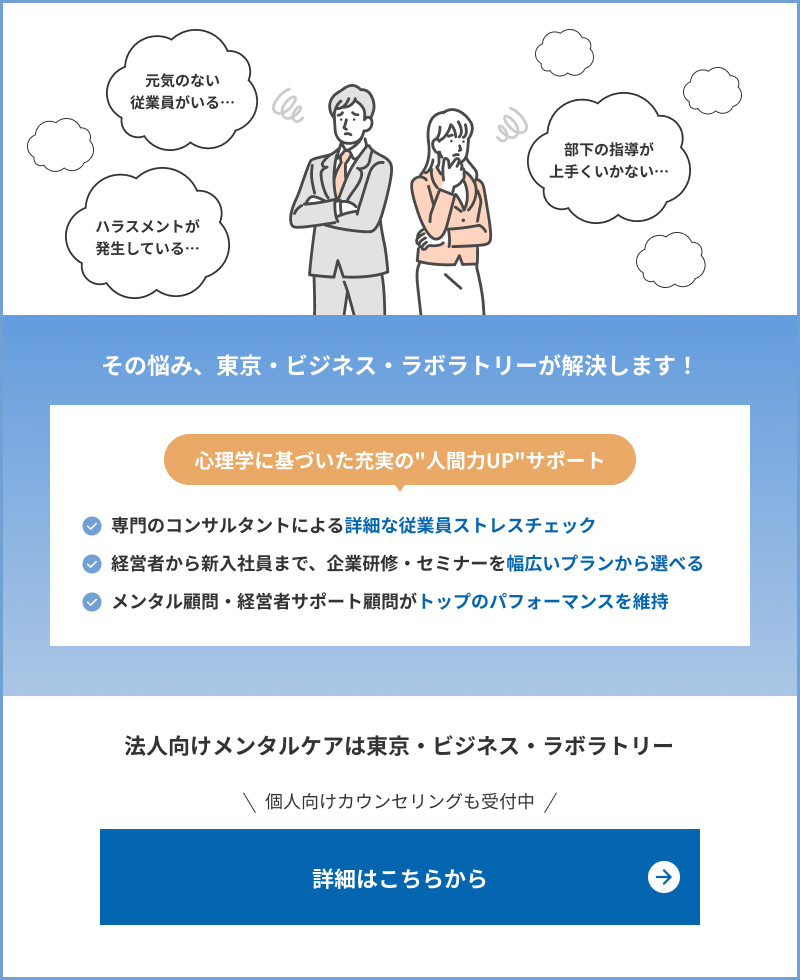目次
人材流出が止まらない主な原因6つ

企業における人材流出とは、従業員が離職し、他社へ転職することを指します。厚生労働省が実施した「令和5年雇用動向調査」によると、転職者が前職を辞めた個人的理由として、次のような理由があげられています。
・職場の人間関係の問題
・給料の不満
・労働条件の悪さ
・能力や資格を活かせない環境
・業務内容への興味の欠如
・企業の将来への不安 など
自社の人材流出が止まらない場合、これらの要因が複合的に作用している可能性が高いといえます。それぞれの項目を掘り下げてみていきましょう。
参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
職場の人間関係が良くない
職場の人間関係への不満は、最も多くみられる離職理由のひとつです。人間関係が悪いと感じる具体的な理由として、職場の風通しが悪くコミュニケーションが取れない環境、上司との相性の悪さ、ハラスメントの存在、出産・育児・介護などの事情に配慮してもらえない状況などがあげられます。
特に近年は、リモートワークの普及により、同僚や上司との直接的なコミュニケーションを取る機会が減少し、人間関係の希薄化が進んでいる企業も多く見受けられます。人間関係に不満がある状況では、従業員にストレスが蓄積され、仕事へのモチベーションが著しく低下します。
このような状況が続くと、メンタルヘルスの問題に発展する場合もあり、結果として離職を決意する従業員が増加してしまいます。人間関係の改善は、単に個人の問題ではなく、組織全体の課題として捉える必要があります。
給料が安い
仕事内容や責任の重さと給料のバランスが取れていない場合も、離職する従業員が増える傾向にあります。給与額だけでなく、各種手当や福利厚生なども含めた総合的な待遇の問題が関わってきます。
特にノウハウやスキルを保有している即戦力人材は、中途採用市場での評価が高いため、より良い待遇を求めて転職するケースが多く見られます。同業他社と比較して相場よりも給与額が低い場合、物価上昇に比例して給与が増えない状況、残業代が適切に支払われていない場合などでは、人材流出が止まらなくなる可能性が高くなります。
労働条件が悪い
労働条件の悪さも人材流出を招く大きな要因です。具体的には、長時間労働が常態化している状況、パワハラやセクハラの問題を抱えている職場環境、業務負荷が高すぎる状況、休暇を取得しづらい雰囲気などがあげられます。
現代では、働き方改革や労働環境の改善に積極的に取り組む企業が増えている中で、このような劣悪な労働条件を放置する企業は、人材が流出する状況を自ら作り出しているといえます。従業員の健康と働きがいを重視し、持続可能な働き方を実現することが求められています。
能力・個性・資格を活かせない
自分の能力やスキル、資格が活かせないと感じて離職する従業員も少なくありません。具体的には、自分の能力を超えた量の業務を一方的に割り振られるケース、せっかく取得した資格を活かす機会が与えられないケースなどがあります。
能力や資格などが十分に活用できない環境では、従業員のやりがいやモチベーションが著しく低下するため、離職者が増加しやすくなります。また、評価基準が曖昧で、自分の能力を正当に評価されていないと判断された結果、より適切な評価を受けられる環境を求めて離職する場合もあります。
業務内容に興味がもてない
業務内容に興味を持てず、もっとやりがいを感じられる仕事に就きたいと考えて離職するケースも存在します。単調な仕事が多く変化に乏しい業務、スキルやノウハウが身に付かない業務などでは、従業員の成長意欲が満たされません。
また、希望していた職種や部署に配属されず、不満やストレスを抱えながら働き続けることで、最終的に離職を決意する場合もあります。従業員のキャリア志向や興味関心を理解し、可能な限り本人の希望に沿った配属や業務アサインを行うことが大切です。
企業の将来に不安を感じる
企業の将来性への不安も人材流出を招く重要な原因のひとつです。保守的な体質で変化に対応できない企業、明確なキャリアパスが提示されていない企業などでは、従業員が将来への不安を感じやすくなります。
また、スキル習得の機会や研修制度の不足により、従業員が成長を実感できない状況では、自身の将来性に対する不安を覚えて離職するパターンもあります。
人材流出が止まらないことで企業が抱えるリスク
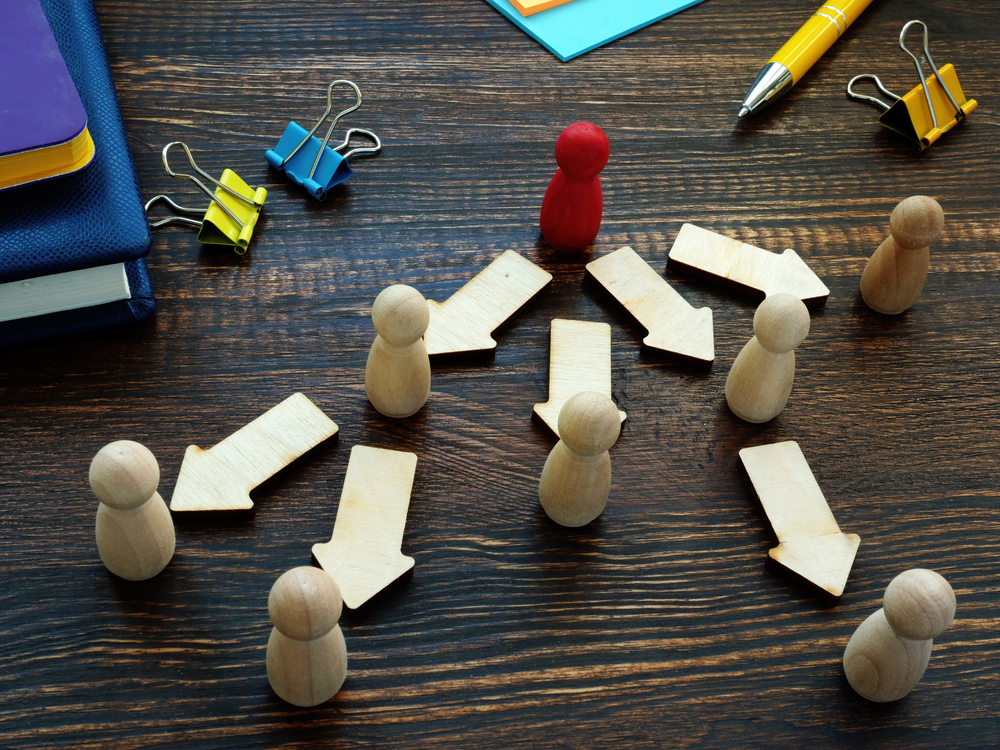
人材流出が継続すると、企業にとって深刻な悪影響をもたらします。単に人手が足りなくなるだけでなく、組織全体の機能低下や競争力の減退など、多面的なリスクが発生します。
労働力が不足する
人材が流出した場合、労働力の不足が懸念されます。また、不足を補うために採用活動を行ったとしても、自社に適合する人材をすぐに確保できるとは限りません。運良く新しい人材を採用できたとしても、業務に慣れ、戦力として機能するまでには相当な時間を要します。
労働力不足が長期化すると、既存の従業員により大きな負担がかかることになり、その結果としてさらなる人材流出を招くという悪循環に陥るおそれがあります。
採用・教育コストが増える
人材を補充するために採用活動を行えば、その分の採用コストが発生します。求人広告費、人材紹介会社への手数料、面接や選考にかかる時間的コスト、内定者への対応費用など、さまざまな経費が必要となります。
さらに、採用後の教育や研修にも相当なコストがかかります。新入社員の教育には、指導者の時間、研修資料の作成、教育プログラムの実施など、多くのリソースが必要となり、企業の負担が増大します。
従業員のモチベーションが下がり生産性が落ちる
人材流出が続く企業では、残された従業員のモチベーションが低下しやすくなります。同僚の離職を目の当たりにすることで、自分も同じような状況に陥るのではないかという不安が生まれ、仕事への取り組み姿勢が消極的になりがちです。
また、人手不足により一人当たりの業務負担が増加し、作業効率も低下するため、組織全体の生産性が大幅に落ちることになります。
顧客やノウハウが流出する
人材が流出すると、その従業員が築いてきた顧客との関係性や、長年培ってきた業務上のノウハウが競合他社に流出してしまう可能性があります。特に、社内で中心的な役割を担ってきた優秀な人材が離職した場合、その後の企業活動に及ぼす影響は計り知れません。
顧客情報や技術的なノウハウの流出は、企業の競争力を著しく低下させ、業界内での優位性を失わせる要因となります。場合によっては、業績の悪化や市場シェアの減少など、経営に直結する深刻な問題を引き起こすリスクもあります。
企業のイメージが低下する
離職率が高い企業は、外部から見て何らかの問題を抱えている企業として認識されがちです。取引先や顧客からの信用が低下し、ビジネス上の機会損失につながる可能性があります。
さらに、採用市場における企業の評判も悪化し、求人を出しても応募者が集まらないという状況に陥る場合もあります。インターネットやSNSの普及により、企業の評判は以前よりも速く広範囲に拡散されるため、イメージの回復には長期間を要することが多いのが現実です。
人材流出を防ぐための対策

人材流出を防ぐためには、原因を正しく把握し、組織全体で取り組む必要があります。以下に示すような対策を総合的に実施し、従業員の満足度と定着率の向上を目指しましょう。
社内のコミュニケーション活性化を図る
社内のコミュニケーションが活発な企業では、人材が流出しにくいという特徴があります。良好なコミュニケーションは従業員のモチベーション維持や、必要な情報の共有を促進する効果があります。
具体的な施策として、部署を超えて気軽にコミュニケーションできるリフレッシュスペースの設置、社内SNSやチャットツールなどのコミュニケーションツールの活用が効果的です。テレワークを導入している企業では、遠隔でも円滑に交流できる仕組みづくりがポイントとなります。
定期的な懇親会やチームビルディング活動の実施なども、コミュニケーション活性化に寄与します。
給料や評価制度を見直す
収入や評価に不満を抱える従業員は多く、給料や評価制度の見直しは人材流出防止に極めて有効な手段です。まず、同業他社と比較して給与水準が適切かどうかを定期的に検証し、必要に応じて調整を行うことが重要です。
給与決定においては、従業員の貢献度や成果を適切に反映させる仕組みを構築し、透明性のある評価基準を明確に示すことが大切です。経営者や管理者の主観に偏らない、客観的で納得感のある評価制度を整備することで、従業員の満足度向上につながります。
また、基本給だけでなく、各種手当や福利厚生も含めた総合的な待遇の改善を検討することで、より効果的な人材定着が期待できます。
労働環境を改善する
パワハラや長時間労働などの問題がある場合は、早急に改善に取り組む必要があります。ハラスメント防止のためのガイドライン策定や相談窓口の設置、労働時間の適正化など、従業員が安心して働ける環境づくりが重要です。
福利厚生の充実や多様な働き方ができる環境の整備も効果的です。休暇が取りやすい制度の導入、テレワークや時短勤務の選択肢の提供など、ワークライフバランスを取りやすい企業は人材が定着しやすい傾向があります。
キャリア開発を支援する
スキルアップやキャリアアップを支援する取り組みを導入することで、従業員の成長意欲を満たし、人材流出を防ぐことができます。研修制度の充実、明確なキャリアプランの提示、専門スキル習得の機会提供などが効果的です。
従業員が「この会社で成長できる」と実感できる環境を整備することで、人材流出のリスクを大幅に軽減できます。社内での対応が困難な場合は、外部の専門研修機関を活用することも有効な選択肢といえるでしょう。
キャリア開発支援なら、東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の企業研修がおすすめです。
課題や経営の方針をヒアリングした上で、各企業様向けにカスタマイズした研修プログラムを提供いたします。世界基準の手法とノウハウを学べるため、堅実な成果につながるでしょう。
まとめ
人材流出は企業にとって深刻な問題ですが、原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで防ぐことができます。職場環境の改善、給与制度の見直し、コミュニケーション活性化、キャリア開発支援など、多角的なアプローチが重要です。従業員一人ひとりが働きがいを感じられる環境づくりに取り組むことで、人材の定着率向上と企業の持続的成長を実現できるでしょう。