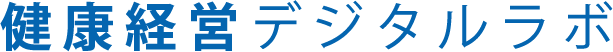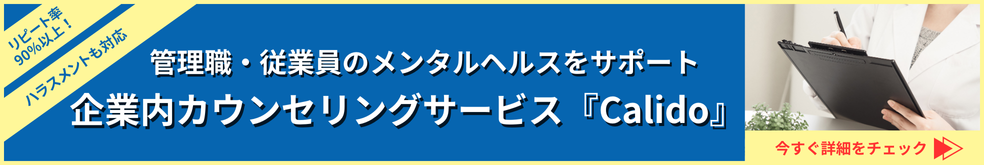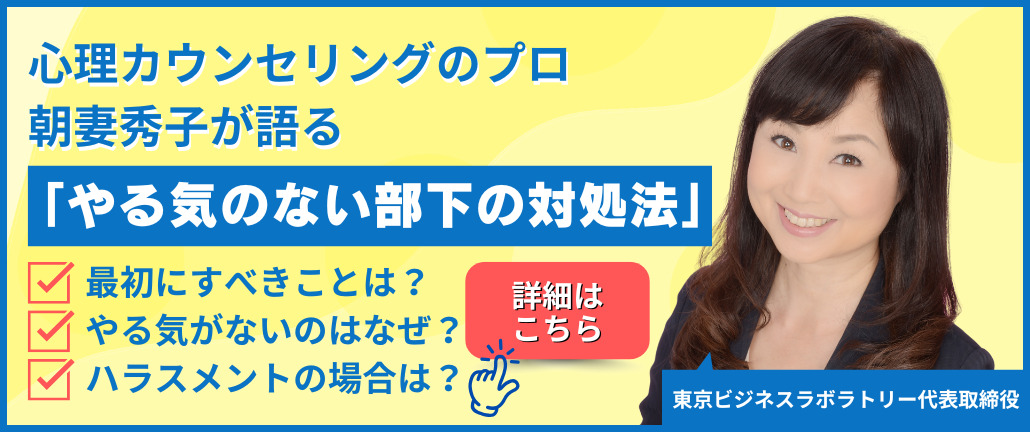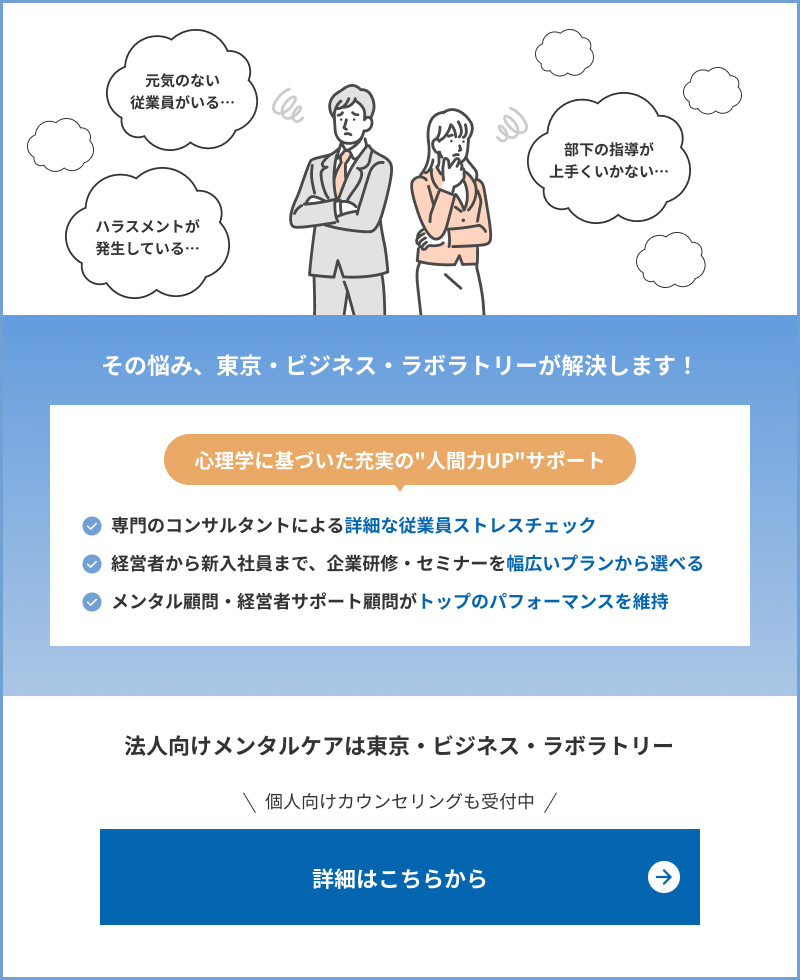目次
部下が相談なしで退職する3つの原因
部下が相談なしで退職する原因は、いくつか考えられます。原因を知るとその後の対応が見えてくるため、知っておきましょう。
原因1|人間関係に不満がある
退職を決断する理由に多いのが、人間関係の問題です。年齢に関わらず、人間関係に不満をもっている方は少なくありません。
すべての人間関係はコントロールできませんが、せめて直属の上司と部下は良好な関係を築いておきましょう。
上司と部下が良い関係ではないと、部下に相談されずにそのまま退職を決断されることになりかねません。
原因2|給与・労働条件に不満がある
給与や労働条件も、よくある退職理由のひとつです。特に、給与、労働条件は会社に相談しづらい部分であり、不満をため込んで突然退職する原因となります。
特に、休みがなかなか取れない状況だとストレスをため込みやすく、相談する前に退職されてしまう可能性が高いです。
原因3|仕事にやりがいを感じない
仕事にやりがいを感じられないと、退職を考え始めます。仕事のやりがいは、特に熱心で上昇志向な方が求めがちです。
行動力がある方は、相談せずに転職先を見つけてしまう場合があります。組織にとって優秀な人材が辞めてしまうことはできる限り避けるべきです。
他にも、部下が相談なしで退職する原因があります。「部下の退職理由、本当は自分のせい?信頼される上司になる3つの方法」で詳しく解説しているのでご覧ください。
部下が相談なしで退職する5つの前兆
部下が相談なしで退職する場合は、前兆があるケースも多いです。前兆を知っておけばあらかじめ対策できるため、把握しておきましょう。
前兆1|業務への意欲が無くなってきた
退職を考えると、現在の業務への意欲が無くなってきます。次の転職先や転職活動のことを考え、仕事が手につかなくなる場合も多いです。
具体的には、コミュニケーションがそっけなくなったり、積極性が無くなったりなどです。
部下の仕事への取り組み方に変化が出てきたら、注意して見てみましょう。
前兆2|ネガティブになってきた
ネガティブになってくることも、前兆のひとつです。職場に不平不満があって退職を考えている場合、愚痴や不満がこぼれてくる場合があります。
特に退職の意志を固めていると、自分はもう関係ないという意識が芽生えてきます。そのため、今まで抑えていたネガティブな発言や行動が表に出てくることも多いです。
部下が急にネガティブになったら、積極的にコミュニケーションを取ってみましょう。
前兆3|遅刻や欠勤が増えた
遅刻や欠勤が増えると、何かしら問題を抱えている場合が多いです。
何もせずに放っておくと、退職してしまうかもしれません。
特に、メンタル面に問題を抱えている方は、遅刻や欠勤が増えがちです。兆候が出てきたら、話を聞くなどしてみましょう。
前兆4|定時前の行動が変わった
定時前の行動が変わったら、要注意です。特に、今まで残業をしていた方が一切残業しなくなったら、注意したほうが良いでしょう。
すでに転職活動を始めている方は、面接などの時間を確保するため、なるべく早く帰ろうとします。残業を拒否したり定時前から帰り支度を始めたりするようになった場合は、一度話を聞いてみましょう。
前兆5|仕事をほかの人へ回すようになった
仕事をほかの人へ回すようになったら、注意しましょう。これは、すでに転職活動を始めている方に多い前兆です。
普段の業務をこなしながら転職活動をするのは、時間的にも体力的にも大変です。そのため、ほかの人に仕事を回してなるべく余裕をつくっている可能性があります。
仕事をほかの人へ回すようになった部下がいたら、一度話してみると良いでしょう。
部下に事前相談なしで退職したいと言われたときの対処法3ステップ
部下に事前相談なしで退職したいと言われたときは、適切な対処が必要です。適切な対処法を知らないと焦ってしまうため、事前に把握しておきましょう。
ステップ1|話を聞く
まずは、なぜ退職したいと思ったのか、理由を聞きましょう。退職したいと思った理由が分からなければ、取るべき対応も分かりません。
話を聞いているときは、さえぎらないようにします。聞きたいことがあっても、必ず最後まで話を聞いてからにしましょう。
ステップ2|退職を回避する方法を話し合い、引き止める
話を聞いたら、退職を回避する方法はないか話し合ってみましょう。もし、改善できる部分が退職の原因であったならば、引き止めることができます。
例えば、給与に不満があるならば上司を通して経営陣に話す、仕事内容に不満があるならばヒアリングして希望に近い仕事を振るなどです。
基本的には部下に会社を辞められると困るため、引き止めましょう。引き止める際は、部下がいかに会社にとって重要な人物かを伝えるのがポイントです。
ステップ3|上司に報告する
話し合い後は、退職の意向を受けたことを経営陣などの上司に相談しましょう。部下の退職は会社にとって大きなことなので、上司への相談は必ずするべきです。
ただ、中には勝手に経営陣へ報告することに、部下側はプライバシーが守られていないと感じるケースもあります。
念のため、上司への相談の必要性を説明してから相談すると安心でしょう。
部下の退職時の注意点とリスク管理
部下を引き止められず、退職届が出された場合の対応も重要です。ここでは、部下が退職したときの注意点とリスク管理について解説します。
即対応が肝心
部下が退職届を提出したら即対応しましょう。記載されている内容をチェックして、人事部などの担当部署に送ります。
また、部下との面談を行い、退職までの引継ぎのスケジュールを立てましょう。業務への影響を冷静に見極め、滞りなく引継ぎが進むよう対策を講じることが重要です。
組織内の士気を下げない
誰かが退職すると、組織全体の士気が下がることがあります。特に何も情報がないと悪影響が出やすくなるため、「個人的な理由での退職」など、必要な範囲で情報を公開しましょう。
また、残された従業員の負担が増えないように、フォロー体制を構築することも重要です。
放置すると他の従業員にマイナス感情が広がりやすくなるので、こまめにミーティングや声かけを行うなどして、意識的にコミュニケーションを取りましょう。
トラブルを未然に防ぐ
退職届提出後の面談の際に、退職日や引継ぎスケジュール、有休消化などについて部下の合意を得ておきましょう。
退職条件が不明確なままだと、後にトラブルが起こるリスクがあります。第三者の立会いの下で詳細を決めていき、記録を残しておきましょう。
また、部下が持つ業務関連のノウハウや、企業内の機密情報・個人情報などの不正利用を防ぐための対策も必要です。秘密保持誓約書を提出してもらうなど、証拠となり得る記録を残しましょう。
部下に相談なしで退職されるのを防ぐ4つの離職防止策
部下に相談なしで退職を告げられたときには、適切な対応が必要です。しかし、あらかじめ相談なしでの退職をされないよう、離職防止策を実行しておくと良いでしょう。
防止策1|コミュニケーションの場を定期的に設ける
コミュニケーションの場を定期的に設けると、離職を防止できる可能性があります。相談なしで退職を告げられるのは、コミュニケーション不足の場合が多いです。
コミュニケーションが取れていないと、部下が退職の前兆を出していたとしても気づくことができません。
まずはコミュニケーションの場を定期的に設けて、部下の様子がわかる状況を作りましょう。日々のコミュニケーションも大事にすると、部下側も相談しやすくなります。
防止策2|定期的にストレスチェックなどの診断を行う
ストレスチェックなどの診断は、定期的に行うようにしましょう。診断を行うと、部下が抱えている悩みを見つけやすくなります。
診断では、なかなか上司には相談しづらいことも見えてきます。急な退職を防ぐには、部下のメンタルヘルス管理は重要です。
防止策3|業務内容や待遇を見直す
業務内容や待遇は、部下が不満を抱きやすいです。そのため、定期的に業務内容や待遇を見直すと、急な退職を防げる可能性があります。
ただ、業務内容や待遇は、現場の声が最も参考になります。見直す際は、必ず現場の声を聞くようにしましょう。
防止策4|相談窓口を設ける
相談窓口を設けることも、離職防止策のひとつです。たとえ不満があっても、普段一緒に働いている上司には相談しづらいと感じる方もいるでしょう。
相談窓口を設けると、上司や同僚には相談しづらいことも話してくれます。不満をため込まなければ、急な退職を防げるでしょう。
まとめ
部下が相談なしで退職すると、組織全体に影響を及ぼしてしまいます。部下がいつでも悩みを相談できるよう、どういったことに悩んでいるのか気づける環境、相談しやすい環境を整えることが大切です。
ただ、部下との関わりが難しいと感じている方もいるでしょう。そのような場合は、外部の企業研修導入をおすすめします。東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では心理学のメソッドで育成のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください