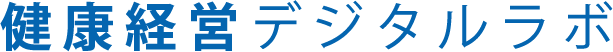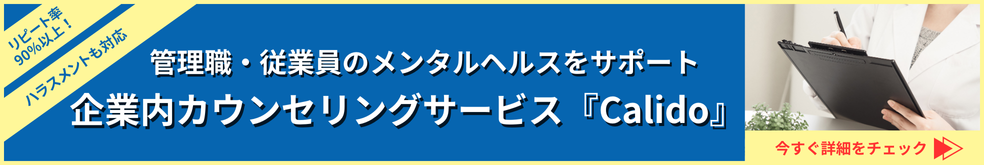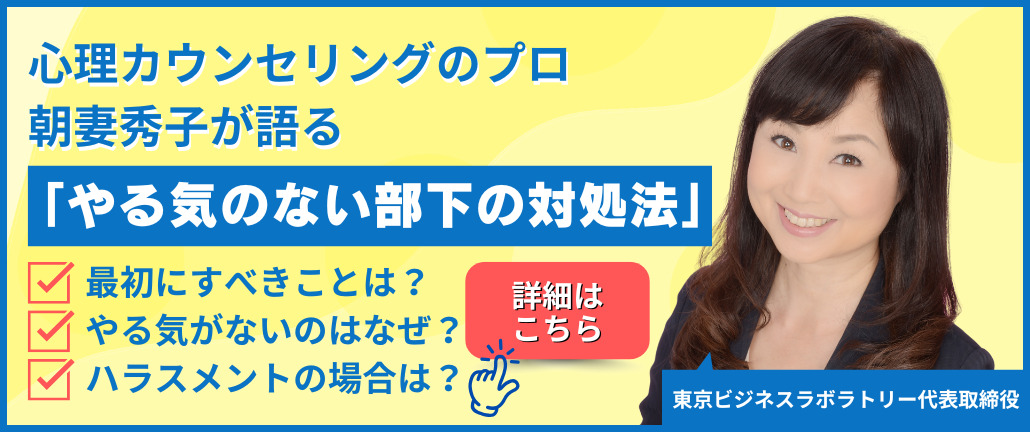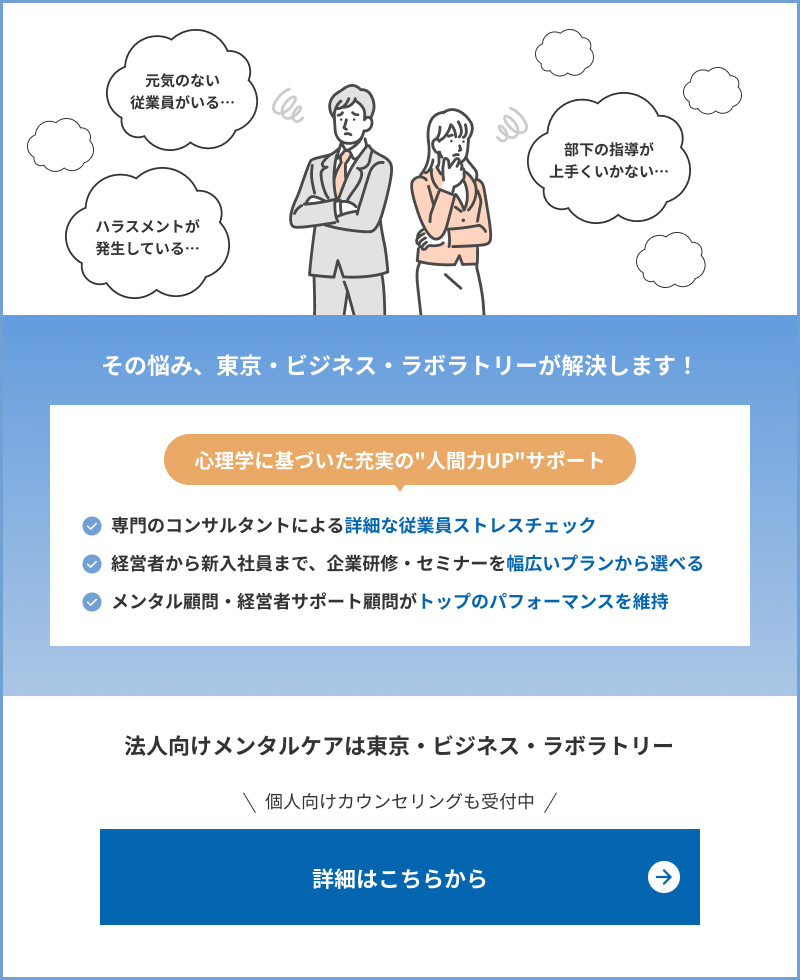目次
部下からのパワハラ(逆パワハラ)の定義
部下からのパワハラ(逆パワハラ)とは、部下から上司に向けて行われるパワーハラスメントです。
パワーハラスメントは上司から部下へ行われるものとされてきましたが、近年は部下から上司へのパワーハラスメントも増えてきており、問題視されています。
パワーハラスメントについては、厚生労働省によって次のように定められています。
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
引用元:厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」
上記に当てはまり、部下から上司へ行われているのであれば、部下からのパワハラ(逆パワハラ)になります。
部下からのパワハラが成立する要件
上記で説明したパワーハラスメントが成立する要件について詳しく解説します。
要件1|優越的な関係を背景とした言動
「優越的な関係を背景とした言動」によるパワハラとは、立場の違いを利用した侮辱する発言や不必要な仕事や作業を行わせることです。一般的には上司が部下に対して優位な立場になりますが、必ずしも役職で優位性が決まるとは限りません。
例えば、部下が専門的なスキルを有しており、その能力を活用して職務遂行しないと業務が進まないケースは、部下が上司より優位な立場になります。このケースにおいて上司への侮辱発言や業務の強要は、パワハラと認定されます。
要件2|業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」を、部下が上司に対して強要した場合はパワハラと認定されます。
例えば、部下が上司に対して自分の昼食を購入するように強要するケースがあげられます。当然ですが、他者の昼食の購入は「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」です。部下が上司に対して、これを強要した場合はパワハラと認定されます。
要件3|労働者の就業環境が害されるもの
「労働者の就業環境が害されるもの」の意味は、パワハラを受けたものが精神的もしくは身体的に負担を感じること、職場環境が不快なものになることと定められています。
例えば、部下が上司に対して威圧的な態度をとり続けたとします。上司は部下に対して萎縮してしまい、コミュニケーションができなくなるかもしれません。部下の存在が目に入るだけで緊張して、通常の業務に支障をきたすおそれもあります。
このケースは部下の言動によって精神的な苦痛を受け、職場環境が不快になっているためパワハラと認定されます。
部下からのパワハラに該当する4つの事例

部下からのパワハラは判断しづらい場合もあるでしょう。そこで、部下からのパワハラに該当する4つの事例を紹介します。
事例1|すべての言動にパワハラだと言われる
すべての言動に対して「パワハラだ」と言われる場合は、部下からパワハラを受けているといえます。
部下の立場を逆手に取り、何でもかんでもパワハラだと訴えて精神的優位に立とうとする事例です。
このようなケースはパワハラの基準のひとつである「職場環境を悪化させる行為」に該当するため、早急に対応しましょう。
事例2|暴言・暴力
暴言・暴力は上司・部下関係なく、明確なハラスメントです。放置するとエスカレートする可能性があるため、すぐに対処する必要があります。
具体的には、はたく・殴るなどの行為、「黙れ」など精神的に追い詰める発言などが該当します。
暴言・暴力を日常的に受けると正常な判断力を失い、うつ状態になる方も少なくありません。
事例3|指示に従わない・無視する
上司は部下に対して指揮監督権があるため、部下が指示に従わなかったり無視したりするケースは、部下からのパワハラに該当します。
特に、特定の上司の指示のみ断ったり無視したりなどが繰り返し行われる場合です。
仕事がスムーズに進まず、多大な影響を及ぼすため、適切に対処する必要があります。
事例4|集団で嫌がらせをされる
部下複数名から嫌がらせをされるいじめ行為は、パワハラと認定されます。具体的には、部下全員で特定の上司を無視する、悪口をいうなどです。
会社内で居場所をなくし、精神的に追い詰められてしまうこともあります。同調圧力で数が増えていく場合もあるため、少人数でも日ごろから注意すべきでしょう。
部下からのパワハラが発生する3つの原因
部下からのパワハラが起きるときには、何かしら原因が隠れているかもしれません。ここからは、部下からのパワハラが起きる3つのパターンを紹介します。原因を知れば、対処法も見えてくるため、状況を確認してみましょう。
原因1|部下の能力が上司よりも高い
上司より部下の能力が高いと、部下からのパワハラが起きやすくなります。能力の高い部下は上司に対する尊敬が薄く、指示の無視や暴言などで見下し、反抗的な態度をとる場合があります。
特に、中途採用の部下で起きやすいため、注意が必要です。自身も勉強しスキルアップするなどの努力する姿勢を見せるようにしましょう。
原因2|上司のマネジメント力不足
上司のマネジメント力不足が原因で、部下からのパワハラが起きるケースがあります。近年はハラスメントが問題視されつつあるため、一人ひとりにさまざまな配慮が求められます。
パワハラになるかもしれないと怯えている上司も多く、部下に問題があっても黙認するケースも少なくありません。そうすると部下の管理ができなくなり、ハラスメントを起こしやすくなります。
原因3|部下のハラスメントに対する知識不足
そもそも、部下がハラスメントに対して知識不足の可能性があります。自分のしている行為がパワハラと認識しておらず、今後改善する見込みも低いと思われます。
そういった場合は、研修を行うのもひとつの手です。自分の行為で上司がどう感じるか、どのような行為がパワハラに該当するのかを知ってもらいましょう。
部下からのパワハラへの対処法5選
部下からパワハラがあった場合には、適切に対処する必要があります。部下からのパワハラへの対処法は、下記の5つです。
・部下と話し合う
・記録を残す
・誰かへ相談する
・会社へ防止策を依頼する
・弁護士へ相談し訴訟する
実際に部下からのパワハラで悩んでいる上司は、すぐに実践してみましょう。
対処法1|部下と話し合う
まずは、部下との話し合いによる解決を目指してみましょう。お互いのコミュニケーション不足が原因でパワハラが生じている可能性があるため、相手の意図を知る必要があります。
話し合いの際には、相手の意見をよく聞きましょう。相手の考えを知れば、パワハラが起こった原因がわかる場合があります。
対処法2|記録を残す
どの部下がいつ、どのような言動をとったかなどの記録を残しておきましょう。もし、第三者機関への依頼や裁判などになったときに、証拠があるかは重要です。
上司へ相談するにしても証拠があった方が動いてくれるため、メモや音声、動画などの証拠は残しておきましょう。
対処法3|誰かへ相談する
一人で抱えきれない場合は、誰かに相談しましょう。第三者へ相談すると解決できることもあるため、なるべく早く相談するのがポイントです。
相談先は社内の人事や、労働局の専門家などがおすすめです。信頼できる人に相談し、適切な対処を仰ぎましょう。
会社内に相談できる人がいない場合は、都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」に相談するのがおすすめです。都道府県労働局では、パワハラを始めとした問題の相談受付だけではなく、都道府県労働局長による助言や指導、紛争調整員会の斡旋も案内されています。
出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
対処法4|会社へ防止策を依頼する
部下からのパワハラに対し、会社へ防止策を依頼するのも手です。会社のルールや体制がパワハラの原因になっている場合もあるため、制度づくりも大事な要素になります。
具体的には、相談窓口の設置や教育・研修などがあげられます。実情を説明し、会社として動いてくれるように話してみましょう。
2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法によって、企業は「パワハラ防止のための措置」を講じることが義務付けられています。それまでは努力義務のみ課せられていた中小事業主についても、2022年4月1日より義務化されました。
会社にパワハラを相談できる窓口がないのは、パワハラ防止法違反です。会社は従業員を守るために、パワハラ相談の窓口を設置して、状況を正確に把握して対応しなければなりません。
もし、会社にパワハラ防止策を依頼して断られた場合は、パワハラ防止法違反であることを伝えた上で対応を打診してください。
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
対処法5|弁護士へ相談し訴訟する
会社が対応してくれない、慰謝料を請求したいなどの場合は、弁護士へ依頼して訴訟を起こす方法もあります。
弁護士へ依頼すれば、適切なアドバイスをしてくれます。ただ、費用や手間もかかるため、最終手段として考えましょう。
部下からのパワハラを放置するのは危険!

部下からのパワハラを放置するのは危険です。部下は自分の行動をパワハラと認識していない可能性があり、さらにエスカレートするかもしれません。上司に対してだけではなく、同僚や新入社員にパワハラをするおそれがあります。
パワハラが長期化すると、上司のメンタル不調や職場環境悪化の原因にもなります。業務に支障をきたすおそれもあり、元の職場環境に戻すためには時間がかかるため、デメリットしかありません。
会社としても安全配慮義務違反や使用者責任に問われる場合があります。このように、部下からのパワハラを放置すると、さまざまな悪影響があります。
パワハラを受けている上司が我慢すれば良いという問題ではありません。問題を解決するために、パワハラの当事者だけでなく、会社全体が素早く行動する必要があります。
部下からのパワハラに対処するならTBLの企業サポート・カウンセリングが最適
部下からのパワハラを防止するのであれば、外部の企業研修を導入するのもひとつの手です。客観的な視点から部下の指導方法が学べます。
外部の企業研修なら、ぜひ東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)をご利用ください。東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では、プロフェッショナルの心理カウンセラーが在籍しており、心理学のメソッドを活用した企業のメンタルサポートやストレスチェックを実施しています。部下からのパワハラに対する相談も可能です。部下への正しいコミュニケーションの仕方や上司としての立ち振る舞いも学べます。パワハラをする部下への対処法に悩んだら、どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ
部下からのパワハラを受けていると、自身が精神的に追い詰められるだけでなく、組織の雰囲気も悪くなります。職場の環境が悪ければ離職率もあがり、人手不足から業績悪化にも繋がります。パワハラに該当する行為を受けた場合は、速やかかつ冷静に対処するようにしましょう。