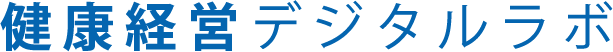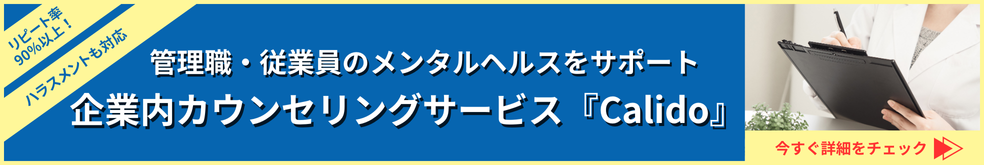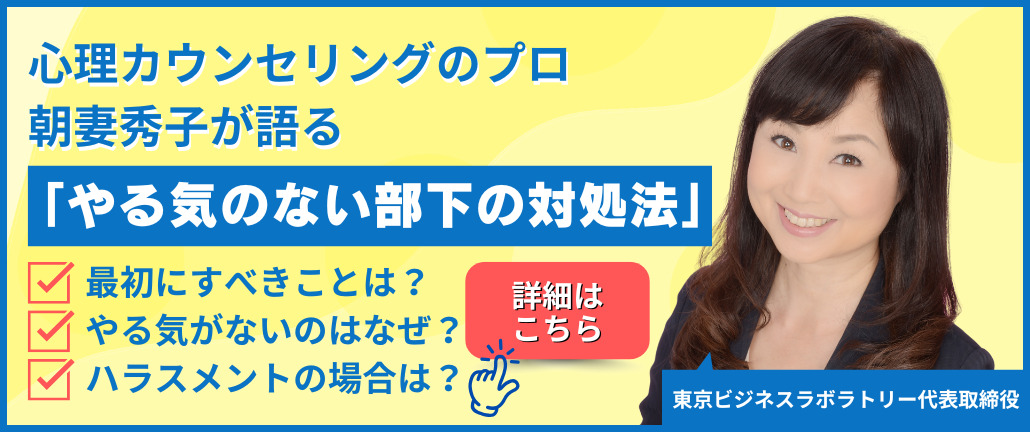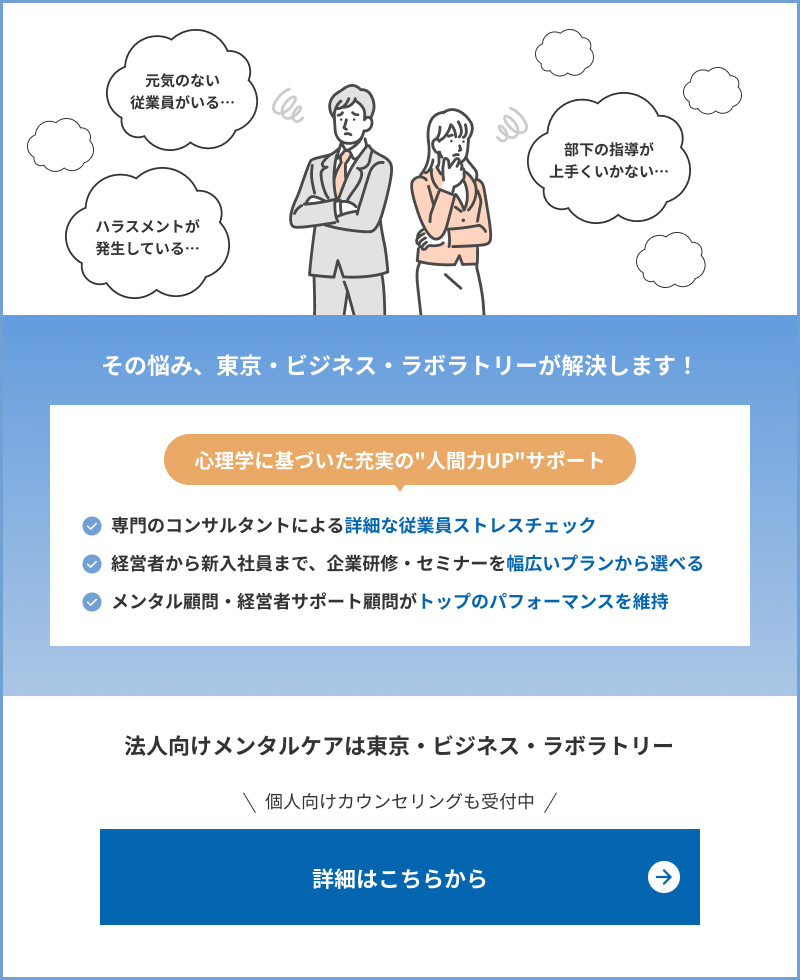目次
パワハラに当たらない事例5選

最近ではハラスメント防止対策が強化され、職場でのコミュニケーションに気を使う場面が増えています。上司としての正当な指導や業務上必要な行為は、適切な方法で行えばパワハラには当たりませんが、不安に思う方もいるでしょう。ここでは、パワハラに該当しない具体的な事例を5つ紹介します。
【事例1】ルールや社内規定を守らない部下に注意した
部下が遅刻を繰り返したり、無断で欠勤したりなど、会社のルールを守らない場合に注意することは、パワハラには当たりません。
また、社内の機密情報を外部に漏らすなど、社内規定を守らない場合に注意することも同様に、パワハラには当たりません。これは上司としての職務の範囲内の行為だからです。
会社のルールを守ることは社会人として当然のことであり、それを守らない部下に対して注意や指導を行うのは上司の責任です。ただし、注意をする際に気を付けることがあります。
例えば、怒鳴ったり、脅迫したり、暴言を吐いたり、暴力をふるったりすると、それはパワハラと認定される可能性があります。冷静に事実を伝え、なぜそれが問題なのかを説明し、今後どうすべきかを具体的に伝えるようにしましょう。
【事例2】意図せず身体に接触した
オフィス内の曲がり角でぶつかってしまうなど、過失によって身体に接触した場合は、パワハラには当たりません。これは小さな事故として扱われるものです。
接触してしまった場合はすぐに謝罪し、相手の状態を確認するなど、誠実な対応をすることが大切です。ただし、意図的に身体に触れる行為は、パワハラやセクハラとして認定されるため注意しましょう。
職場では必要以上に相手の身体に触れることは避け、お互いのパーソナルスペースを尊重する意識を持つことが重要です。
【事例3】業務上必要な個人情報を同意の上で聞いた
業務を円滑に進めるために必要な個人情報を、部下の同意を得た上で聞くことはパワハラに該当しません。
通常、家庭の事情などプライベートな情報を聞くことは避けるべきです。しかし、病気や家庭の事情などで特別な配慮をするために必要な情報を聞くことは、パワハラには当たりません。
ただし、下記のような場合はパワハラになる可能性があるので注意しましょう。
・部下が同意していないのに執拗に個人情報を聞き出そうとする
・業務に関係のない個人的な情報を聞く
・聞いた個人情報をほかの人に漏らす
個人情報を聞く際は、なぜその情報が必要なのかを説明し、業務上必要な範囲内に留めることが重要です。
【事例4】部下の成長のために難易度の高い仕事を任せた
将来的に管理職を任せたいという目的で、部下の成長のために少し難易度の高い仕事を任せることは、パワハラには当たりません。部下の能力を伸ばすためのチャレンジングな仕事の割り当ては、むしろ育成の一環といえます。
ただし、下記のような場合はパワハラになる可能性があります。
・部下のレベルに見合わない、著しく難易度が高すぎる仕事を強制的に任せる
・「育成」と称して、大量の仕事を一方的に押し付ける
・失敗した場合に厳しく叱責する
部下に難しい仕事を任せる際は、事前に丁寧に説明し、必要なサポートを提供しながら、少しずつステップアップできるように配慮することが大切です。また、進捗状況を定期的に確認し、適切なフィードバックを行うことも重要です。
【事例5】別室で研修や指導を行った
新入社員を別室で研修したり、重大なミスをした部下を別室で指導したりすることは、パワハラには当たりません。通常業務とは異なる内容の研修や指導を行う場合、部下本人にも周囲の従業員にも配慮して別室を使用することは、むしろ適切な対応といえます。
例えば、ミスについて指導する際に、オープンスペースで行うと本人が恥ずかしい思いをするだけでなく、周囲の従業員の業務も妨げてしまうでしょう。そのため、プライバシーに配慮して別室で行うことは理にかなっています。
ただし、下記のような場合はパワハラになる可能性があります。
・正当な理由なく長期間にわたって別室で通常業務とは異なる作業をさせる
・別室に隔離して、ほかの従業員との交流を意図的に断つ
・別室で怒鳴ったり、脅したりする
別室での指導を行う場合は、その目的と期間を明確にし、部下に対して丁寧に説明することが重要です。また、別室での指導が終わった後のフォローアップも忘れないようにしましょう。
上司が把握すべきパワハラの定義と6つの類型

パワハラに当たらない行為を理解するためには、そもそもパワハラとは何かを正確に把握しておくことが重要です。ここでは、厚生労働省が定めるパワハラの定義と6つの類型について解説します。
厚生労働省が定める「パワハラの定義」とは?
厚生労働省は、下記の3つの要素をすべて満たす行為を「パワーハラスメント」と定義しています。
1.優越的な関係を背景とした言動であること
2.業務の適正な範囲を超えたものであること
3.労働者の就業環境が害されるものであること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
「優越的な関係」とは、単に上司と部下という関係だけではなく、先輩と後輩、同僚間でも、職務上の地位や人間関係、専門知識などの優越性を背景に行われるものを含みます。
例えば、長年勤務している社員が新入社員に対して行う行為や、特定の専門知識を持つ社員がほかの社員に対して行う行為も含まれるのです。
また、通常は部下から上司への行為はパワハラに当たらないと考えられがちですが、複数の部下が結託して上司に対して嫌がらせを行うなど、部下が優位に立つ事情がある場合は、パワハラに該当する可能性があります。
「業務の適正な範囲」については、業務上必要かつ相当な範囲で行われる指導や注意は、相手が不満に感じたとしてもパワハラには該当しません。例えば、ミスをした部下に対して冷静に事実を指摘し、改善を求めることは、適切な方法で行われる限り、パワハラには当たりません。
出典:厚生労働省「パワーハラスメントの定義について」
パワーハラスメントの「6つの類型」
厚生労働省は、パワーハラスメントを下記の6つの類型に分類しています。
1.身体的攻撃:殴る、蹴る、物を投げるなどの暴力行為
2.精神的攻撃:長時間の叱責、罵倒、脅しなど
3.人間関係からの切り離し:職場での孤立、無視、排除
4.過大な要求:達成不可能な仕事を無理に押し付けたり、仕事を妨害したりすること
5.過小な要求:能力に見合わない簡単な仕事を与えて、成長の機会を奪うこと
6.個の侵害:プライバシーに関わる不適切な質問や、私生活に対する不当な干渉
これらの類型を理解し、自分の言動がこれらに該当しないよう注意することが、上司として重要です。また、ほかの従業員間でこのような行為が行われていないかにも目を配り、健全な職場環境を維持することも大切です。
上司ができるパワハラ対策の具体例

パワハラを防ぐためには、企業全体での取り組みが欠かせません。ここでは、上司が実施できる具体的な対策を紹介します。
パワハラへの理解を深める
パワハラの予防には、まずその理解を深めることが大切です。上司自身が「パワハラとは何か」を把握していなければ、無意識のうちにパワハラを引き起こすこともあります。したがって、企業全体でのパワハラ研修を実施し、上司や従業員がパワハラの定義や事例について学べる環境をつくることが重要です。
外部の研修を受けることも有効です。東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では、パワハラへの理解を深めるための研修を提供しています。企業における具体的なケースに即した対応方法を学べますので、ぜひご相談ください。
>>東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の研修・セミナーはこちら
社内アンケートを実施する
社内アンケートを定期的に実施し、職場内のパワハラの実態を調査することも有効な対策です。アンケートの結果から、自分では気づかなかった問題点が見えてくることもあります。
アンケートの実施方法としては、匿名での調査が望ましいですが、従業員数が少ない場合には面談形式にするなど、自社に合った方法を考えることが大切です。
また、アンケートを実施して終わりではなく、パワハラが起きていることが把握できた場合は、速やかに対処することが重要です。問題を放置すると、職場環境の悪化や従業員のメンタルヘルスの低下、離職率の上昇などにつながる可能性があります。
関連記事:「社内アンケートで本音は聞ける?アンケートのコツと作り方を紹介」
注意・指導の目的を明確にする
部下への注意や指導は、部下を成長させ、業務の質を向上させるためのものであり、自分のイライラや不満を晴らすためのものではありません。感情的になって部下に当たるのは、パワハラと判断されかねません。
注意や指導を行う際は、下記のポイントを心がけましょう。
・注意・指導の目的を明確にし、それがしっかりと伝わるように冷静に話す
・具体的な事実に基づいて指摘し、なぜそれが問題なのかを説明する
・改善すべき点だけでなく、良かった点も伝える
・一方的に話すのではなく、部下の言い分も聞く姿勢を持つ
・人格を否定するような発言は避け、行動に焦点を当てる
・ほかの従業員がいない場所で行う
適切な注意・指導は、部下の成長につながり、信頼関係の構築にも役立ちます。感情に任せた指導は逆効果になることを念頭に置いておきましょう。
「パワハラのグレーゾーン」にも対処できるようにしておく
パワハラかどうか判断が難しいグレーゾーンの行為も存在します。例えば、ほかの従業員の前で叱ることや、業務上必要な範囲を超えた厳しい言葉で指導することなどです。
判断が微妙だからといって放置すると、部下が精神的に追い詰められたり、職場全体の雰囲気が悪化したりするおそれがあります。グレーゾーンにも対応できるような対策や制度を整えておくことが大切です。
まとめ
パワハラに当たらない行為について理解することは、職場の管理職として適切な指導を行うために欠かせません。パワハラを避けるためには、上司自身がその定義と各類型を理解し、部下への指導を冷静かつ適切に行うことが求められます。
また、職場の健全な環境を守るためには、パワハラ防止のための教育やアンケート実施、指導方法の見直しが欠かせません。上司として部下との信頼関係を築き、良好なコミュニケーションを保ちながら、パワハラを未然に防ぐ対策を講じましょう。