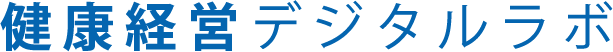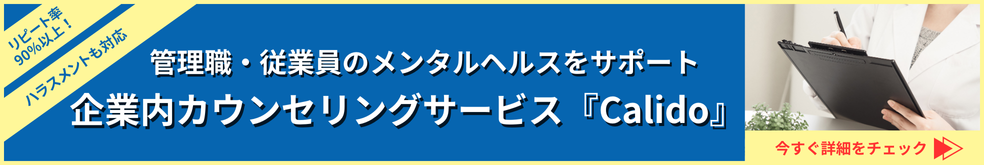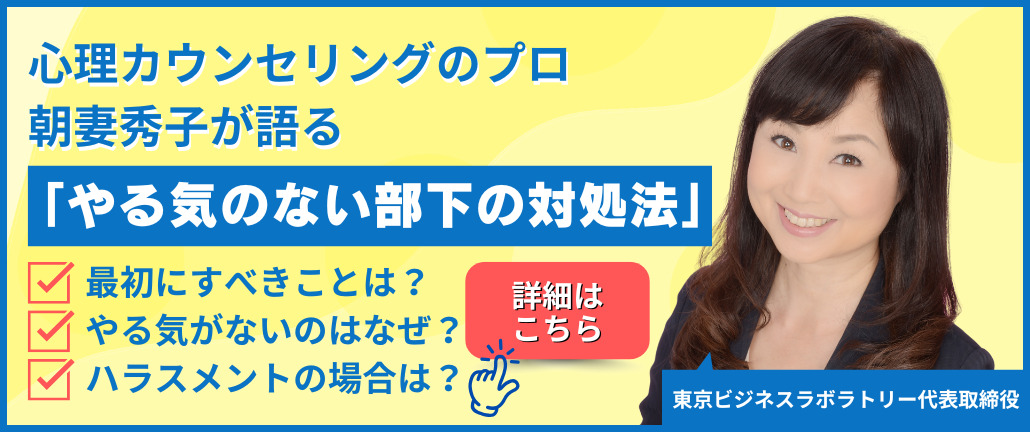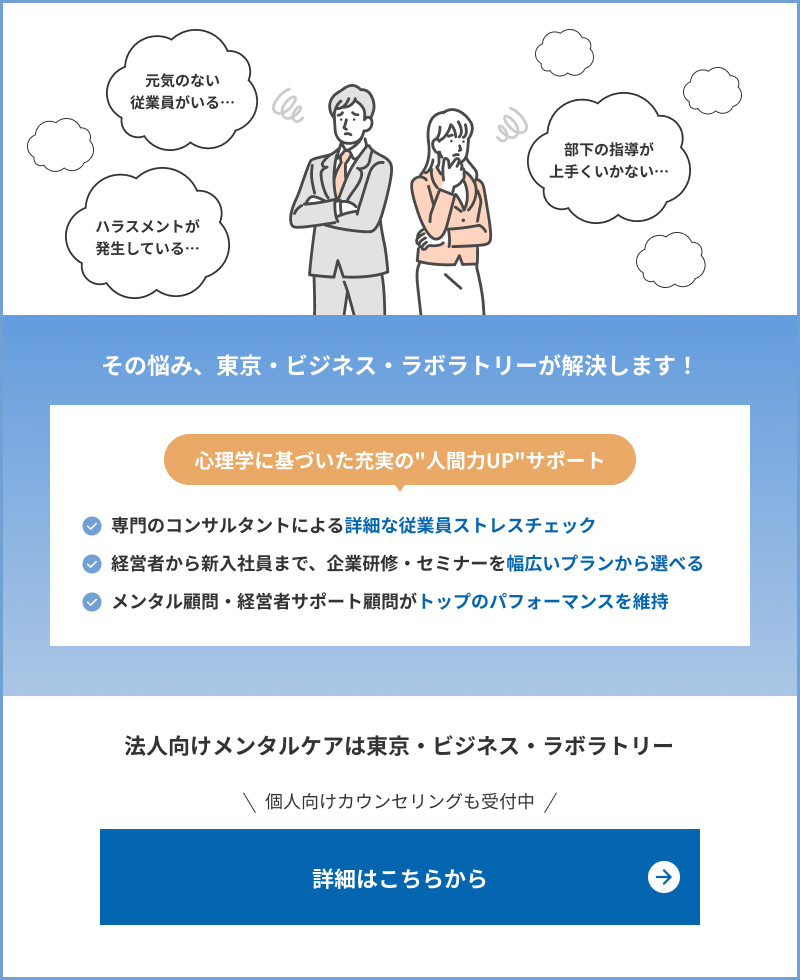目次
会社で起こるハラスメントの種類10選

会社で発生するハラスメントは多岐にわたりますが、そのなかでも特に注目すべきものを紹介します。
パワハラ(パワーハラスメント)
パワハラとは、職位や立場を利用して、部下や同僚に対して不当な言動を行い、精神的または身体的な苦痛を与える行為です。業務の適正な範囲を超えて、例えば過度な業務命令や無理な要求をすることが該当します。パワハラが発生する背景には、上司の不適切な指導方法や、職場内の力関係の偏りが関係していることが多いです。
例えば、部下に対し無理なノルマを押し付けたり、度を超えた叱責を繰り返したりすることがパワハラに該当します。こうした行為は、被害者の心身に深刻なダメージを与え、最終的には退職せざるを得ない状況になることもあるのです。
関連記事:
「部下の叱り方のコツとは?信頼関係を築きながら成長を促す方法を紹介」
「部下からのパワハラを防ぐには?原因や事例、対処法を解説」
セクハラ(セクシャルハラスメント)
セクハラは、性的な内容の発言や、意に反する性的な行動を強要することを指します。これは、男性から女性だけでなく、女性から男性へのセクハラも含まれます。
セクハラには、対価型と環境型があり、前者は昇進や仕事の機会と引き換えに性的関係を迫るもの、後者は不快な性的な発言や行動が職場内で日常的に行われることにより環境が悪化するものです。
例えば、女性社員の外見に対して不適切なコメントをすることや、不必要な身体への接触行為が該当します。これは被害者にとって非常に不快で、職場環境が悪化する原因となります。
モラハラ(モラルハラスメント)
モラハラは、精神的な虐待や心理的な攻撃を加える行為を指します。パワハラとは異なり、モラハラは上司と部下の立場に関係なく、個人間で行われる場合もあります。被害者の人格や価値観を否定するような言動、無視や差別的な扱いなどが典型的なモラハラの例です。
例えば、上司が部下に対して繰り返し「お前はできない」と能力を決めつける言動や、意図的に仕事を与えないなど、相手を精神的に追い詰める行為がモラハラにあたります。モラハラによって被害者は自信を失い、仕事に対する意欲も低下することになります。
モラハラが起こる原因や解決方法は下記の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:「「どうしてモラハラは起きる?」原因と解決方法を解説」
マタハラ(マタニティハラスメント)

マタハラとは、妊娠や出産、育児休暇などに対して不適切な言動を行うことを指します。具体的には、妊娠や育児を理由に不利な扱いを受けたり、仕事を強要されたりすることがあります。こうした言動は、女性社員のキャリアに大きな影響を及ぼすことがあり、精神的にも辛い状況を引き起こすのです。
例えば、育児休暇を取得したいと伝えた際に、上司から「それでは仕事が回らない」と言われたり、復帰後に仕事の内容が大きく制限されたりする場合などがマタハラに該当します。
パタハラ(パタニティハラスメント)
パタハラは、男性が育児に関わる際に受けるハラスメントです。妻の妊娠や出産、育児に対して不適切な言動が行われることがあります。具体的には、育児休暇を取得しようとした際に職場から否定的な反応を受けることや、育児に参加することを非難されることなどです。
例えば、父親が育児休暇を取ろうとした際「男がそんなことをしてどうするのか」と言われることがパタハラに該当します。このような行為は、男性が育児に関与することへの社会的な理解を妨げ、育児休暇の取得に対する偏見を助長することにつながります。
ジタハラ(時短ハラスメント)
ジタハラは、社員が労働時間を短縮したいと申し出た際に、それを不当に拒否したり、過度に期待をかけたりする行為を指します。例えば、家庭の事情や健康上の理由で時短勤務を希望している社員に対して、上司が不当にその要求を拒否したり、短縮した勤務時間での仕事に対して過度な期待をしたりすることが該当します。
このような状況では、社員のモチベーションが低下し、仕事への意欲が損なわれるでしょう。
フキハラ(不機嫌ハラスメント)
フキハラは、職場で常に不機嫌な態度を取り、周囲の社員に不快な思いをさせる行為です。例えば、上司が常に不機嫌な顔をして仕事をしていると、部下が気を使って無駄にストレスを感じることになります。これが長期的に続くと、職場環境全体が悪化する可能性があります。
不機嫌な態度は無意識に職場の雰囲気を悪化させるため、社員の心理的負担を増加させてしまうでしょう。
アルハラ(アルコールハラスメント)
アルハラは、飲酒を強制することや、飲酒に関して配慮を欠いた言動を行うことです。例えば、社内での飲み会で、飲みたくない社員に無理に酒を勧める行為や、飲まなければ社会的に疎外されるような雰囲気をつくることがアルハラに該当します。
アルハラは、社員のプライバシーを無視し、飲酒ができない理由を尊重しない行為です。
スメハラ(スメルハラスメント)
スメハラは、本人が気づかないうちに発生することが多い、周囲に不快感を与えるようなニオイに関するハラスメントです。例えば、強い香水や体臭が原因で、周囲の社員が不快に感じることがあります。このような状況が続くと、職場の人間関係に悪影響を与える可能性があります。
本人がニオイに無頓着な場合でも、周囲の社員はストレスを感じることが多いため、注意が必要です。
カスハラ(カスタマーハラスメント)
カスハラは、顧客や取引先などが従業員に対して不当な言動を行うことです。例えば、理不尽な内容のクレームや、従業員に対して暴言を吐くなどが該当します。
カスハラは従業員にとって精神的な負担となり、ストレスの原因になります。
会社で起こるハラスメントの対処法

近年では、ハラスメントに対する対応が企業の重要な課題であり、適切な対処が必要です。ここでは、会社でハラスメントが起きないようにするための対処法を3つ紹介します。従業員が安心して働ける環境づくりを進めましょう。
社内の方針を明確にして周知する
まず重要なのは、会社の方針を明確にし、従業員全員に周知徹底することです。具体的には、何がハラスメントに該当するのか、なぜそれが問題なのかを明文化し、全社員に理解させることが大切です。
例えば、セクハラやパワハラといった具体的な行為をあげ、どのような行動がハラスメントとして扱われるかを示すことで、社員が無意識のうちにハラスメントを行うことを防げます。
また、ハラスメントを行った場合の処分についてもあらかじめ決めておき、厳正に対処することを周知することが重要です。このように、会社全体で一貫したハラスメント対策を講じることで、社員の意識が変わり、より健全な職場環境が作られるでしょう。
ハラスメント研修を実施する
ハラスメントに対する知識や認識を深めるために、定期的な研修を実施するのも効果的です。1回限りの研修では不十分な場合が多いため、年に何度かの頻度で定期的に行うことが推奨されます。
研修では、ハラスメントの定義やそれが職場に与える影響を理解させるだけでなく、ハラスメントを見過ごさず、適切に対応する方法を学ぶことができます。また、心理学のメソッドを取り入れた研修を実施することで、社員の心に訴えかけ、より深い理解と意識改革を促進することが可能です。
研修を行うことで、社員一人ひとりがハラスメント問題を他人事としてではなく、自分事として捉えるようになり、職場環境の改善につながります。
関連記事:「ハラスメント研修を実施する目的とは?効果を高める方法を紹介!」
東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では心理学のメソッドを使い、心に働きかける研修を提供しています。さまざまな企業研修プランを用意しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
>>東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の研修・セミナーはこちら
いつでも相談できる環境を整える
ハラスメントの早期発見・対応のためには、被害を受けた従業員がいつでも安心して相談できる環境を整えることが不可欠です。専用の相談窓口を設置し、その存在を全従業員に周知しましょう。
相談窓口の担当者は、秘密保持の徹底と公平な対応ができる人材が適しています。特に従業員から信頼されている方を選ぶことで、相談のハードルを下げることができます。また、相談しやすさを考慮すると、男性・女性両方の担当者を配置することが望ましいでしょう。
相談者によっては同性のほうが話しやすいケースもあるため、選択肢を用意しておくことが大切です。相談内容は厳格に秘密として扱われること、相談したことによる不利益な取り扱いは一切ないことを明確にし、安心して声を上げられる環境を構築しましょう。定期的なアンケートなどを通じて、匿名でも懸念を表明できる仕組みもあわせて検討すると良いでしょう。
まとめ
会社で発生するハラスメントにはさまざまな種類があり、どれも職場環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。適切な対応策としては、会社の方針を明確にし、ハラスメント研修を定期的に実施することが求められます。
また、被害を受けた社員が気軽に相談できる環境を整備することで、従業員が安心して働ける職場を作り上げ、ハラスメントの予防と早期発見につなげることも重要です。ハラスメント問題に対して積極的に取り組み、健全で働きやすい職場作りをともに目指していきましょう。