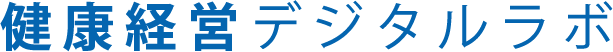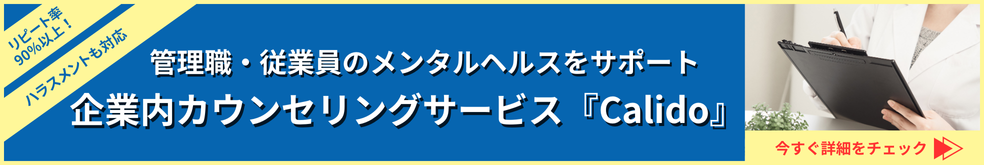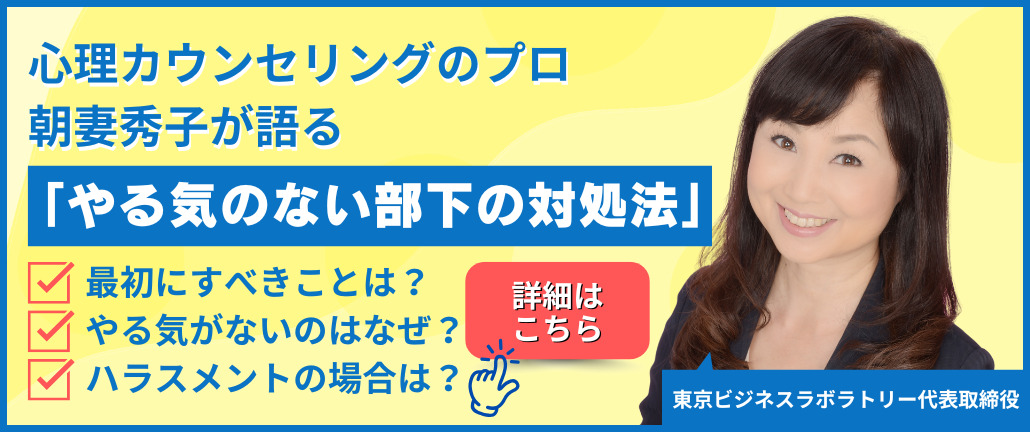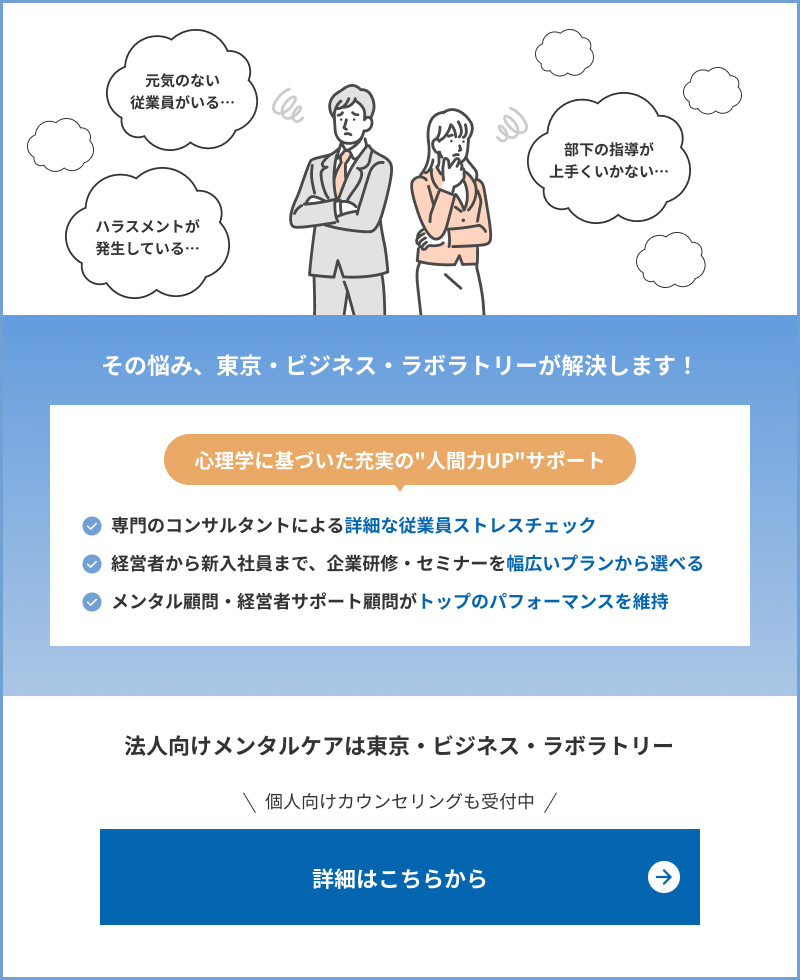目次
部下を評価する目的

上司が部下を評価するおもな目的は、部下の育成です。評価結果を参考に、部下自身も現時点で何ができているのか、できていないこと・不足している部分は何かを自覚しやすくなります。
部下の成長を促すためには、一方的に叱責するのではなく、本人に気付きを与えて自発的に取り組んでもらうことが重要です。上司が正しく評価できる環境なら、部下は自分の現状を客観的に把握でき、フィードバックを参考に次の目標を立てられます。
評価、目標設定、改善、成長の正しいサイクルが確立されれば、徐々に不足していた部分もできるようになります。部下の確実な成長につながり、上司にとっても評価をもとに考え方を伝えやすくなる仕組みの完成です。
部下への評価は「制度設計」が何よりも重要!

上司個人の感覚に任せた評価では、部下の成長にはつながりません。ゴールである部下の成長を実現するためには、適切な制度設計で評価することが大切です。
ここでは、部下への評価で制度設計を重視すべき理由を2つ解説します。
理由1|適正でない評価はモチベーションを下げるため
残念ながら「上司に適正に評価されていない」と感じている部下は一定数存在します。特に、評価基準の不明瞭さに不満を感じることが多いようです。なかには「特定の上司と仲良くするだけで評価が上がる」といった不当な評価を目の当たりにして悩んでいる人もいるでしょう。
自分の努力を適正に評価されていないと感じると、仕事へのモチベーションが下がってしまうおそれがあります。個人的な問題のように感じるかもしれませんが、評価に不満を感じている部下が増えれば、会社全体の士気や生産性の低下が懸念されるでしょう。
もちろん、適正な判断で低評価を与えざるを得ない場合もあるはずです。しかし、部下への評価の伝え方を工夫したり、期待のメッセージを伝えたりする配慮も必要です。
理由2|評価への不満はストレスとなるため
不当な評価に対する不満は、やがて大きなストレスへと発展します。例えば、効率良く仕事を終わらせて定時で帰る人より、必要もないのにゆっくり時間をかけて仕事をして残業する人の方が評価されると、どう感じるでしょうか。前者に該当する人は間違いなく不満を抱えるはずです。
そのような不当な評価は「評価エラー」といい、部下のストレスにつながります。そのままストレスが積もると、最悪の場合退職してしまう人もいるでしょう。有能な人材の離職を防ぐためにも、部下のストレスとなる評価エラーなどの要素は排除しておくことが必要です。
間違っても、個人的な感情で部下の評価を下げるような事例があってはなりません。「過去のたったひとつの失敗に捉われた評価をしていないか」「仲の良い部下に甘い評価をしていないか」など、客観的に評価の公平性を見直してみましょう。
部下を評価する項目は4つ

部下を適正に評価するためには、評価する項目や基準を設ける必要があります。下記の4つの基準を意識して正しく評価しましょう。
1.能力評価
能力評価とは、その業務に必要とされる能力の有無を評価する項目のことです。「目標を達成するために効率の良い計画が立てられたか」「業務を計画通りに実行できたか」などの能力を評価します。
具体的には「企画力」「実行力」「統率力」「豊富な知識」「課題への改善努力」などを総合的に判断します。
2.成果評価
成果評価は、定められた期間内にどの程度の実績を作れたかを評価する項目です。「新規案件を何件獲得できたか」「いくら売り上げたか」などの、目に見える成果を評価します。
主に、営業成績や製造した個数などの「業務目標達成度」や、与えられた問題への「課題達成度」をチェックします。また、担当業務の処理効率や品質などを示す「日常業務達成度」を見ながら、総合的に評価しましょう。
3.情意評価
仕事への意欲や、仲間とのコミュニケーション能力などは情意評価として判断します。勤務態度などを評価しなければならないため、具体的な数値基準がなく曖昧になりやすい項目です。
基本的には、担当している業務への「責任性」やチームとして業務を進める「協調性」、自ら難しいことにチャレンジする「積極性」を評価します。
しかし、評価のためだけに部下を観察しようと思っても本質が見えてきません。部下の職場での立ち回りから判断できるよう、普段から意識してチェックしておきましょう。
4.行動評価(コンピテンシー評価)
コンピテンシー評価とは、特定の人物の行動パターンを基準とする評価方法です。基準となる人物は、仕事において高いパフォーマンスを発揮している社員です。行動を評価する点は情意評価と似ているものの、それぞれ注目するポイントが異なります。
情意評価が積極性や協調性といった内面的な部分に重きを置いているのに対して、コンピテンシー評価は実際の行動や、結果へのプロセスを重視しています。
行動特性に着目した評価を行うときは、抽象的すぎない項目を設定することが大切です。評価項目が抽象的すぎると、結果に対して部下の納得感が得にくくなります。
コンピテンシー評価について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
「コンピテンシー評価とは?メリットや導入の手順・注意点を解説!」
部下を評価する際の基準は?チェック項目を確認しよう

ここでは、制度設計のうち評価基準の設定方法について解説します。
部下を適切に評価することは必要ですが、評価する際は何を基準にすればいいのでしょうか。気になるチェック項目は、下記の通りです。
・出社時間など社内ルールを守っている
・積極的な姿勢で仕事している
・社内の課題を見つけて問題提起ができる
・スキルアップに励んでいる
・ミスをきちんと報告している
・社内・社外の人に丁寧な対応をしている
まず、出社時間や社内規則など、基本的なルールが守れているかを確認してください。どれだけ仕事ができていても、ルールを守れない人は組織にとって悪影響になってしまいます。
基本的なルールが守れていれば、仕事への取り組み姿勢や普段の様子などを見て、さらに評価しましょう。
チェック項目があった方が評価しやすく、人によって基準がばらけることもないため、チェック項目を作ることがおすすめです。
部下を評価するときに押さえておきたい3つのポイント

部下を評価するときには、押さえておくべき3つのポイントがあります。
・ルールに沿って公平に評価する
・本人にも自己評価をしてもらう
・評価基準を共有する
1.ルールに沿って公平に評価する
部下を評価するときは、ルールに沿って公平に評価するようにしましょう。部下の評価は給与などに影響してくるため、ルールに従って正しく評価し、公平性を保つことが重要です。
評価の際は上司の主観的な印象ではなく、数字などの正確な情報に基づいて評価するようにしてください。現状、数字で判断することができなければ、社内の人事評価制度の見直しも検討するべきです。
人事評価制度の作り方に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
2.本人にも自己評価をしてもらう
部下の評価をする際は、本人にも自己評価をしてもらうようにしましょう。自己評価をすると、部下が自分を客観的に見るきっかけになります。
もし、自己評価と他者評価にズレがある場合、その理由を一緒に考え、ズレを埋める方法を検討してください。自分の中の評価と外からの評価のズレが分かれば、今後の業務に活かせます。
また、万が一部下が評価に不満を覚えていれば、すり合わせもできます。
3.評価基準を共有する
どのような点を重視するのか、どのような方法で判断するのか、評価基準はあらかじめ部下にも共有しておきましょう。評価の仕方がわかっていない状態で努力するように言われても、部下は適切な目標設定ができません。目標設定にズレが生じれば、自己評価にも影響を与えます。
近年では、オープンな資料として公開している企業も珍しくありません。しかし、新人や転職者の場合、そもそも資料のありかを知らされていない可能性が考えられます。スタート地点で不用意な差が生まれないように、目標設定を行う段階で資料の保管場所や閲覧方法も共有しておくことが望ましいと言えます。
実際に評価するときも、抽象的ではなく具体的なコメントを意識することが大切です。評価基準のどの部分を根拠に判断したのか、納得感のある内容に仕上げましょう。
どのような根拠をもとに評価したのか明確にすることで、上司も自信を持ってアドバイスでき、部下も納得して評価を受け入れやすいです。
部下を評価するときに注意したいこと

部下を評価するときには、いくつか注意すべきポイントがあります。注意点を知らないと適切に部下の評価ができないため、必ず把握しておきましょう。
部下を評価するときに注意したいことは、下記の3つです。
・評価のバイアスに気を付ける
・フィードバック時にフォローも行う
・評価後の部下のコンディションを把握する
評価のバイアスに気を付ける
部下を評価するときは、評価のバイアスに気を付けましょう。評価のバイアスとは、部下を評価する際に、部下の第一印象や社交性などが評価に影響してしまうことです。
具体的には、仕事で成果を出している人の評価が甘くなったり、新入社員の評価が厳しくなったりします。
評価者自身のスキルや経験をもとに評価してしまい、適切な評価ができないこともあるため、注意しましょう。
フィードバック時にフォローも行う
フィードバックで評価の結果を伝えるときは、ダメ出しにならないようにしましょう。ダメ出しばかりだと部下のモチベーションが落ちてしまうため、褒める点も盛り込むことが重要です。
部下の評価は一度したらそこで終わりではなく、その後の部下の成長を見越してするべきです。部下のスキルアップに役立つ情報を提供するなどして、部下の成長を促してみてはいかがでしょうか。
評価後の部下のコンディションを把握する
評価後の部下の様子について、気にかけておく必要があります。適正な人事評価を心がけていても、部下が必ず納得してくれるわけではありません。公平公正な評価を下しても、不満を覚える部下は一定数存在するものです。
早期に対処するためにも、評価後は部下のコンディションを把握することが大切です。例えば下記のポイントを確認します。
・評価に納得しているかどうか
・評価前と仕事へのモチベーションに変化はないか
・チームや組織への帰属意識に変化はないか
帰属意識の変化は、離職の兆候ともいえます。同じ組織で働き続けたいという部下の気持ちに変化は生じていないか、言動に注視しましょう。
評価が部下にネガティブな影響を与えていると判断できる場合は、具体的なフォローが必要です。
部下への評価コメントを書く際のコツ
部下を評価するときは、点数に加えて上司からのコメントも求められます。評価コメントを書くときは、下記のポイントを意識しましょう。
・評価しているポイントは具体的に書く
・数字・事実をもとに成果を評価する
・課題・問題点は改善案も併記する
部下が結果を参考に改善できるように、どの部分を高く評価しているのか、どの点が改善すべきなのかを具体的に解説することが大切です。
単純に「良かった」と書くのではなく、例えば「どの仕事のおかげで売上が何%上がったのか」「新規顧客が何社増えたのか」など具体的な数字や事実を提示して評価すると納得感が出ます。
課題や問題点も具体的に記載して、今後どのような工夫をすれば改善が期待できるのかアドバイスも添えると、部下も参考にしやすくなります。
評価コメントについて、より詳しく知りたい方は、下記の関連記事もご覧ください。
関連記事:
「言葉で変わる?部下を育てる言葉と気を付けておきたい指導方法」
「360度評価のコメントに悩む!例文を立場別・職種別・評価項目別で紹介」
部下のストレスを軽減して健康経営を目指そう
部下が感じているストレスを軽減したり、健康を重要視したりする姿勢は企業の業務効率化に欠かせません。そのように、健康管理の戦略的実践を「健康経営」といいます。ここからは、経済産業省が定める「健康経営」の内容を解説します。
健康経営とは
健康経営とは、経済産業省が推進する「国民の健康寿命の延伸」の取り組みのひとつです。主に企業が、社員の健康管理を経営的に考えた実践を指します。健康経営では「社員の健康が会社の生産性を上げる」という考え方に基づき、社員の健康への投資を行うことを推進しています。
フィジカル面の健康はもちろん、メンタル面の健康管理も必須です。健康の管理が業務の効率化や離職率の低下につながることから、メンタルヘルス対策を行う企業も多いようです。
また経済産業省では、地域の健康課題への取り組みなど、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を「健康経営優良法人」に選定する制度を設けています。
健康経営優良法人に選ばれると「従業員の健康を大切にしている会社」であることをアピールできるでしょう。
出典:経済産業省「健康経営」
関連記事:「健康経営優良法人のメリットとは?注意点や取得方法まで解説」
健康経営の必要性
多くの企業が人手不足に悩むなか、良い人材を確保するために福利厚生の充実が求められています。離職率を下げるためにも、健康経営を取り入れて社内環境を整える必要があるといえるでしょう。
また、メンタルの健康増進も健康経営の一環です。メンタルケアが生産性の向上や業績アップにつながるため、健康経営を重視するに越したことはありません。
しかし、通常の業務や部下への適正な評価のために、毎日試行錯誤しながら疲弊している上司も多いでしょう。「今の状況を改善したい」「もっと部下の健康やメンタルケアに注力したい」と考える人は、健康経営や部下のメンタルケアに関するセミナー・プログラムへの参加がおすすめです。
東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)では、健康経営に関するマネジメントのお悩みやストレスの問題にも対応しております。メールカウンセリング、対面カウンセリングも可能なのでぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
部下への正当な評価は、管理職の大切な業務です。曖昧な基準や、個人的な感情で評価をつけることはあってはなりません。誰に対しても、能力や成果、情意のポイントを意識して正当な評価を与えましょう。公正な評価は、部下のモチベーションを上げる源となるはずです。
反対に、適切な評価が行われない場合は、部下が不満を感じストレスにつながります。離職率の低下や業務の効率化を図るためには、部下の心身の健康に親身に寄り添う姿勢が大切です。まずは、健康経営に関するセミナー・プログラムへの参加を検討してみてはいかがでしょうか。